ふぞろいな1次試験勉強方法!よっしー編 ~机に向かう勉強時間が確保できない人に~
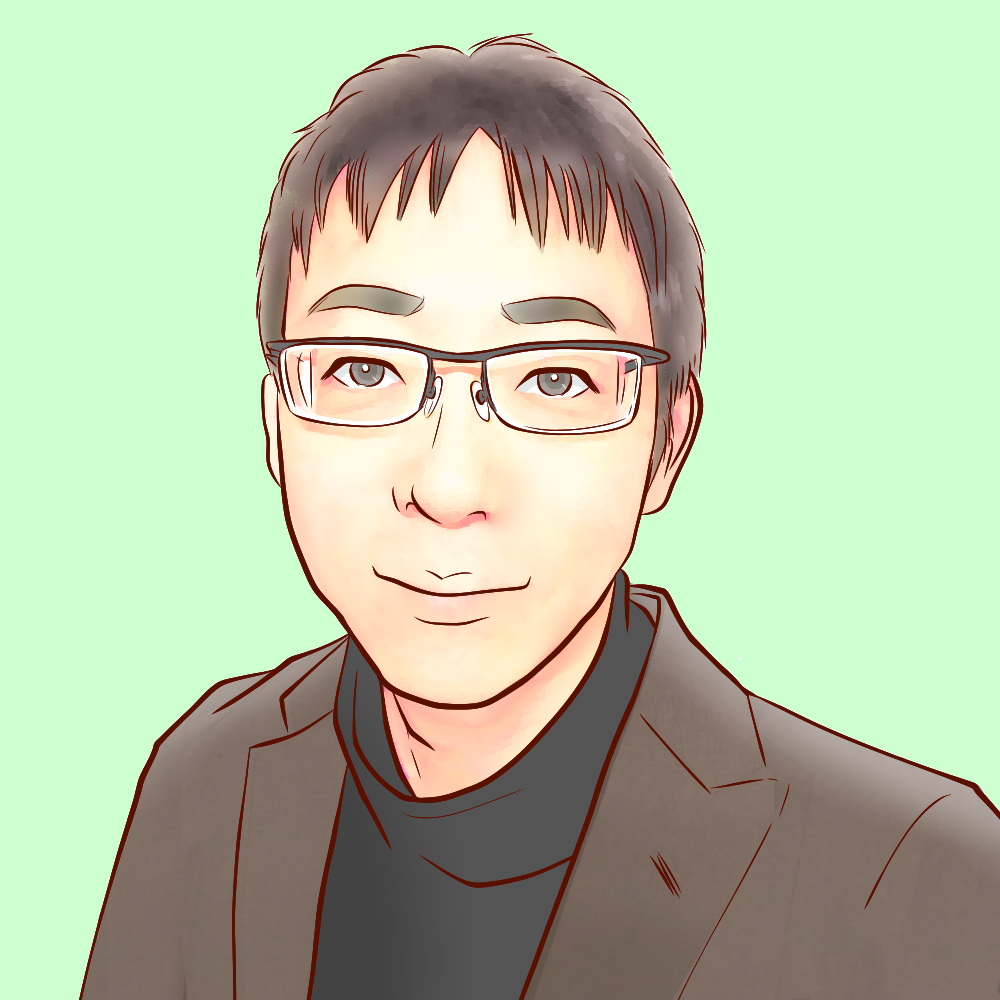
お久しぶりです!資格強者のふぞろいメンバーの中で異色の資格を並べるよっしーです。(何を言っているか分からない方はお手すきの際に自己紹介もどうぞ)
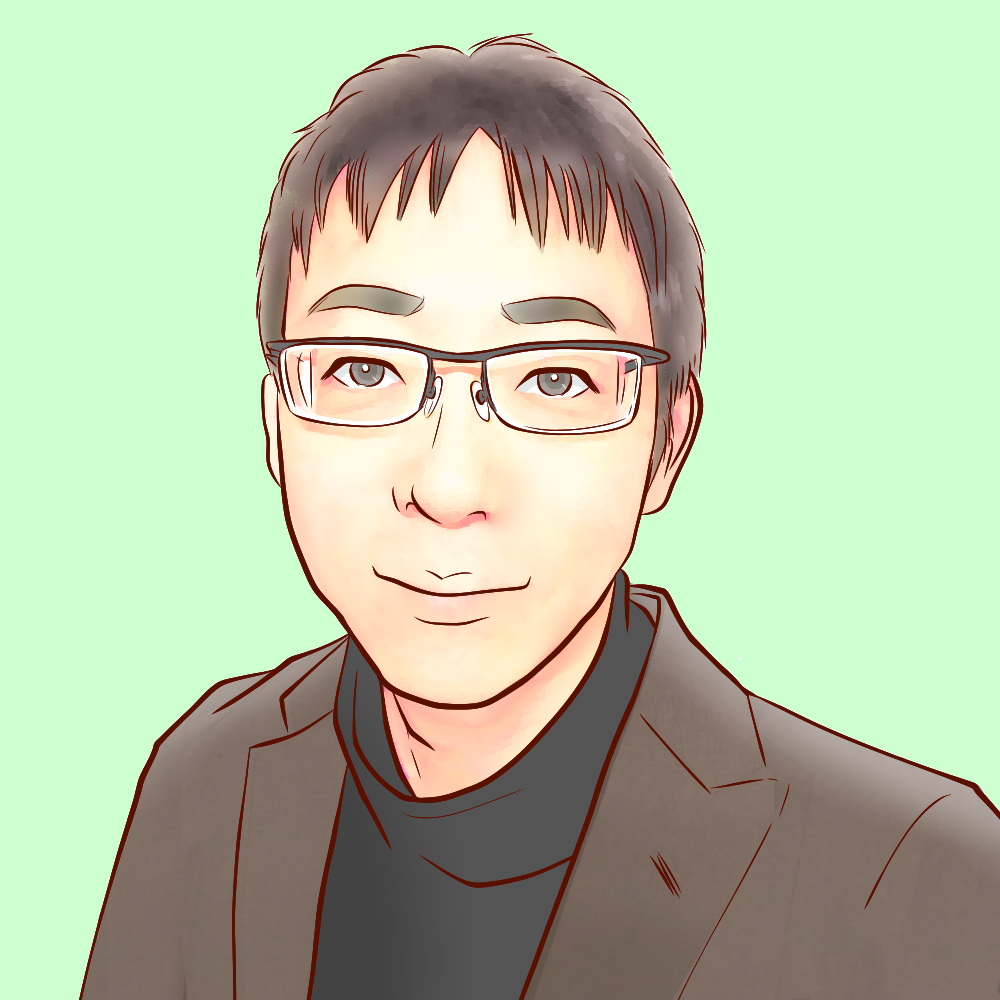
日本酒検定3級受かった(有言実行)!今年中にもう一つくらい受けたい
一次試験の受験申し込みは昨日まででしたが、皆様無事に申し込めたでしょうか?少々手順の多い申し込みが終われば、あとは勉強に専念あるのみです。今からやる気出す、という人もまだまだ間に合うので、頑張って隙間時間を捻出していきましょう。
目次
1次試験結果(※令和4年度)
【合計点】421/600点(自己採点)
【経済学・経済政策】64/100点
【財務・会計】80/100点
【企業経営理論】71/100点
【運営管理】80/100点
【経営法務】68/100点
【経営情報システム】資格による免除
【中小企業経営・政策】58/100点
机に向かう必要はない
通勤に片道2時間程度(しかも複数回乗り換え)かかる私の主な勉強場所は電車の中でしたので、いかにスマホ(時々テキスト)だけで勉強が完結するかを意識して学習を進めました。もし同じような状況の方がいるのであれば、参考になれば幸いです。
使用教材とおおまかな使い方
①テキスト:『最速合格のためのスピードテキスト』(先輩が過去の分を全部譲ってくれたので……)
ざっと一読するためと、出題範囲の確認目的に。
②過去問:『過去問ドットコム』(他の資格でもいつもお世話になっています)
1.科目別にざっと確認し、科目別の戦略検討の事前情報に。
2.過去問回すときに。
③YouTube:『ダンシ君のサブノート』
耳しか使えないとき、やる気が出ないときのインプットに。
④その他参考書:『絵で分かるマクロ経済学』『絵で分かるミクロ経済学』
全力でグラフを理解するために。(経済学・経済政策は経済学・経済政策はとにかくグラフ理解だけに集中しました。これだけで突破したと言っても過言ではありません!)
⑤その他web:色々な専門サイト
テキストに記載されていない最新の情報や、用語などを補うために。
一次試験の戦略と教材の使い方(詳細)
プロローグ: 科目免除のための資格取得
中小企業診断士試験に向けた準備は数年前から始まっていました。私が資格取得を考える際には、いかに科目免除を活かせるかを考えるので、中小企業診断士受験も、その前提条件が応用情報技術者に受かること、という歪な考えでスタートしました。プログラミング言語などは全く理解しないまま、経営戦略とプロジェクトマネジメントだけのゴリ押しで応用情報技術者を取得した私は、満を持して中小企業診断士に挑戦することにしました。こういった背景のため、得点源にするかどうかなど考える余地もなく、当然のように経営情報システムは免除を選択しました。
選択式試験の考え方:○が分かる問題はそう多くなくても良い
※あくまで私個人の考え方なので、興味のある人だけが参考にしていただければと思います。
二次試験や実務においては的確に正解を導いていくことが重要になるかもしれませんが、それは一次試験が終わった後でもできるはずです(私はできませんでしたが、多分できるはずです)。
まず目下のターゲットである一次試験を突破することを目的とした場合、大事なことはいかに「正解を知らなくても正答できる」、つまり「不正解の選択肢を見極められる」ようにすることではないかと私は考えています。そんなことはわかっているよ、という声が聞こえそうですが、理屈上は5分の1の確率を3分の1にでもできれば、40点分を正解するだけであとは確率論で60点に届く計算になるので、不正解が不正解であることをしっかりと理解することは重要であるというのが私の考えです。
勉強の進め方:(時間の関係上)狭く深く
個人差はあると思いますが、私個人はテキストを読んでいても理解が進まない派なので、テキストは最初にざっと目を通した後は、過去問の参考書扱いで活用していました。
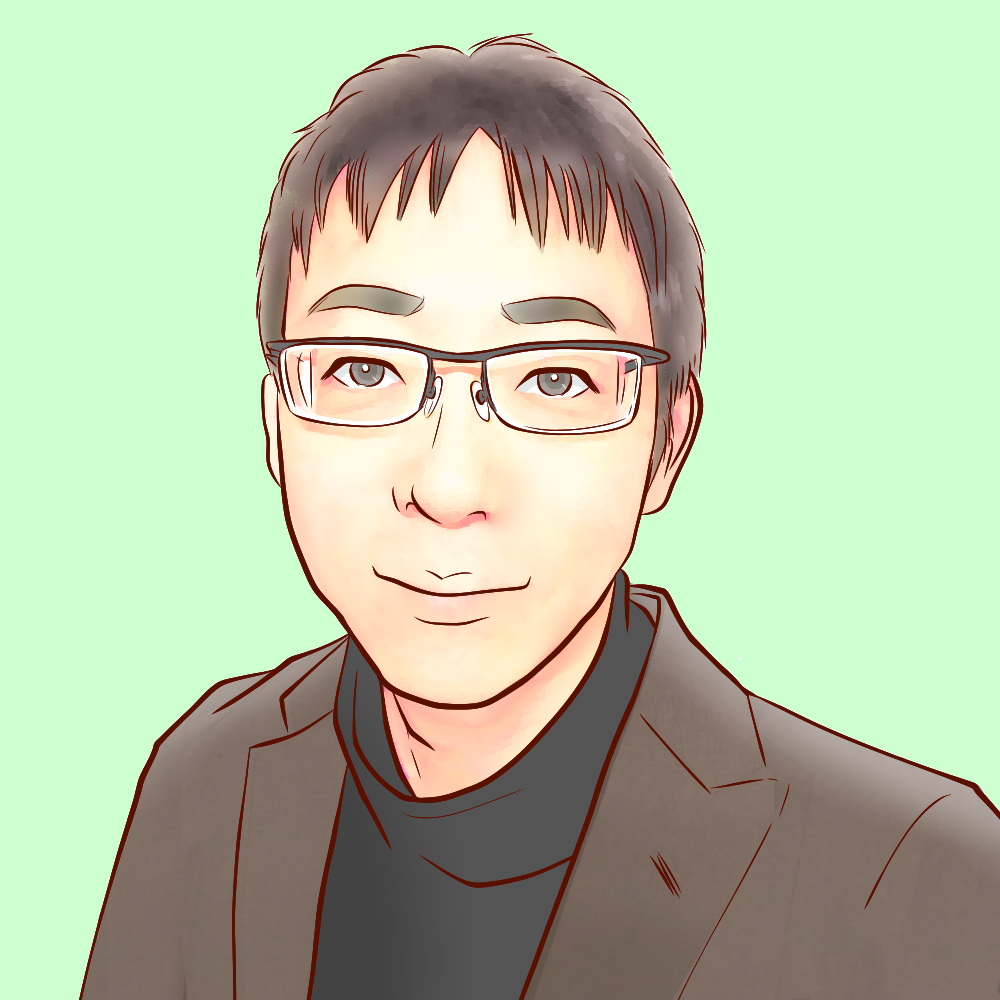
昔は暗記でゴリ押しできたのにね……
①とりあえず、無の状態で過去問1年分を、時間をかけずにざっと目を通してみて、何となくわかる科目(財務・会計、運営管理)は後回しで勉強することにする。
②テキストはどこに何が書いてあるかを把握するために1~2日で1科目読む(基本的には出題範囲の確認が中心)。理解は一旦置いておいて、とにかくまずは一度読み通して全体像を把握しておく。何かこんなページあったかも、くらいの朧げな記憶で進める。
③過去問を実際に解いてみて、「どの範囲が苦手そうか」、「どういう選択肢を出してくるのか(出題者はどこが受験生にとって理解しにくいポイントと考えているのか)」を確認。
④あとはとにかく苦手そうな範囲を中心に過去問を1問ずつ解く→用語がわからない選択肢があれば都度スマホで調べる、という過程を経て、とにかく全ての選択肢が○か×かと、その理由が分かるように進めていきました。
※荷物が重くなるのは嫌なので、テキストは最大でも1冊、基本的にはあまり持ち歩いていません。なので、用語の確認などは大体スマホ上で試験とは関係のない、詳細が説明されているサイトを見に行っており、テキストは家に帰ってから再確認する用でした。
⑤気が向かない時や、家事をしている時などはひたすらYouTubeを2倍速で流し続けていました(夜はほぼエンドレスリピートでした)。五感を使いながら勉強すると効果的だとどこかで聞いたことがあるので、家にいるときは家事をしながら『ダンシ君のサブノート』に声を出して回答することで、五感をフル活用していました。
科目特化の勉強法
基本は上記の進め方だったのですが、数年前のテキストを使用していたこともあり、経営法務と中小企業経営・政策に関しては、最新の法改正だけ別途調べておきました。
また勉強のスタートが遅すぎたこともあり、経済学・経済政策は完全に時間切れでした。なので、とにかく肝だと考えたグラフだけ完璧に理解できれば足切りは回避できるだろうとヤマを張って図書館で何か良い本がないか探していたのですが、思いのほか初学者には理解しやすい内容で幸運でした。
注意点
実際にやってみると分かるかもしれませんが、このやり方をすると過去問1周に結構時間かかります。周回派の人には合わないやり方かなと思います。私は時間がなかったこともあり、とにかく科目も学習範囲も絞って深掘りに注力した形となりましたが、結果として二次試験では遠回りすることにもつながってしまいました……。
ただ、用語の確認をwebで完結してしまえば、どこでもできるやり方ではあるので、10分あれば過去問1、2問の全選択肢を調べることはできます。まとまった時間がなくて今からやる気出してももう間に合わない、と考えている人がもしいるのであれば、少しでも参考になれば幸いです。
終わりに
明日5/31は「あーや」の登場です!とても激務そうなのにどうやって勉強していたのか、受験のトレードオフに一体何を犠牲にしたのか、私も非常に気になります。乞うご期待!





