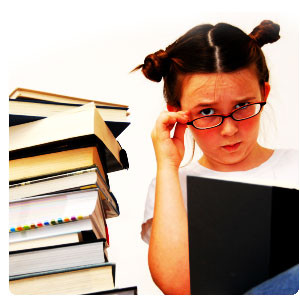合格にはいくつ事例を解くべきか?
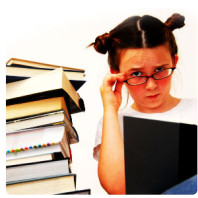
こんにちは。あんどぅです。
いよいよ10月にはいりました。残り3週間ちょっと。どう過ごすか重要です。ここで、
最終的にどのくらい事例演習をすべきか?
を考えてみたいと思います。
夏・秋のセミナーでも何度か話はしましたが、私の経験では「72事例が目安」という事をお話しました。
合格者に聞いてみても、
「そのくらいの数は確かにひとつのラインかもね」
という納得感があるようです。
72事例と言えばⅠ~Ⅳそれぞれ18事例です。過去問5年分を2回、プラス8事例を予備校や模試なので現実的なラインと言えそうです。
ちなみに、私自身は72事例を目指してガリガリやっていたら8月~10月で結果的には100事例を超えていました。
しかし、一方で、合格者には20事例程度だった人もいます。
よって、単純に数の問題だけで考えるのも危険で、72事例にこだわりすぎるのも良くないかもしれません。
どう考えるのが良いでしょうか?
2次試験に必要なスキルを、「知識」と「試験技術」に分けてみます。
知識とは、1次試験の知識に加え「その会社をどうすべきか」と考える知識や経験。
試験技術とは、80分間で必要な読解、検討、記述をする「試験をさばくスキル」。
私はこの2つのスキルのバランスで大きく2つのタイプがあるように思います。
タイプ1: 知識はあるが試験技術が不安な人。
ビジネス経験が多く経営的な感覚を持っているが、 80分のさばき方や効率的な執筆に不安がある人。
タイプ2: 試験技術はあるが知識に不安がある人。
ビジネス経験が少なく、80分のさばき方よりも、本質的にその会社がどうすべきか分からない。
模範解答の意味が本質的・現実としてなかなか腹に落ちない人。
タイプ1の人は、80分でミスなく効率的に精度を上げる必要があるため、数をこなすのが有効かと思います。
一方でタイプ2の人は、数よりも考察に時間をかけて、その事例企業にじっくりと向き合って考えることが有効かと思います。
特に、模試などで表面的には良い点数がとれるけれども本試験でかみ合わない人にはタイプ2の人が多い気がします。
いずれにしても事例の演習数はひとそれぞれですが、自分がどのタイプに属するのか?によって、
少し調節してみてはいかがでしょうか?