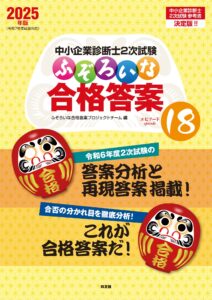自己紹介!3年目受験生さかい編
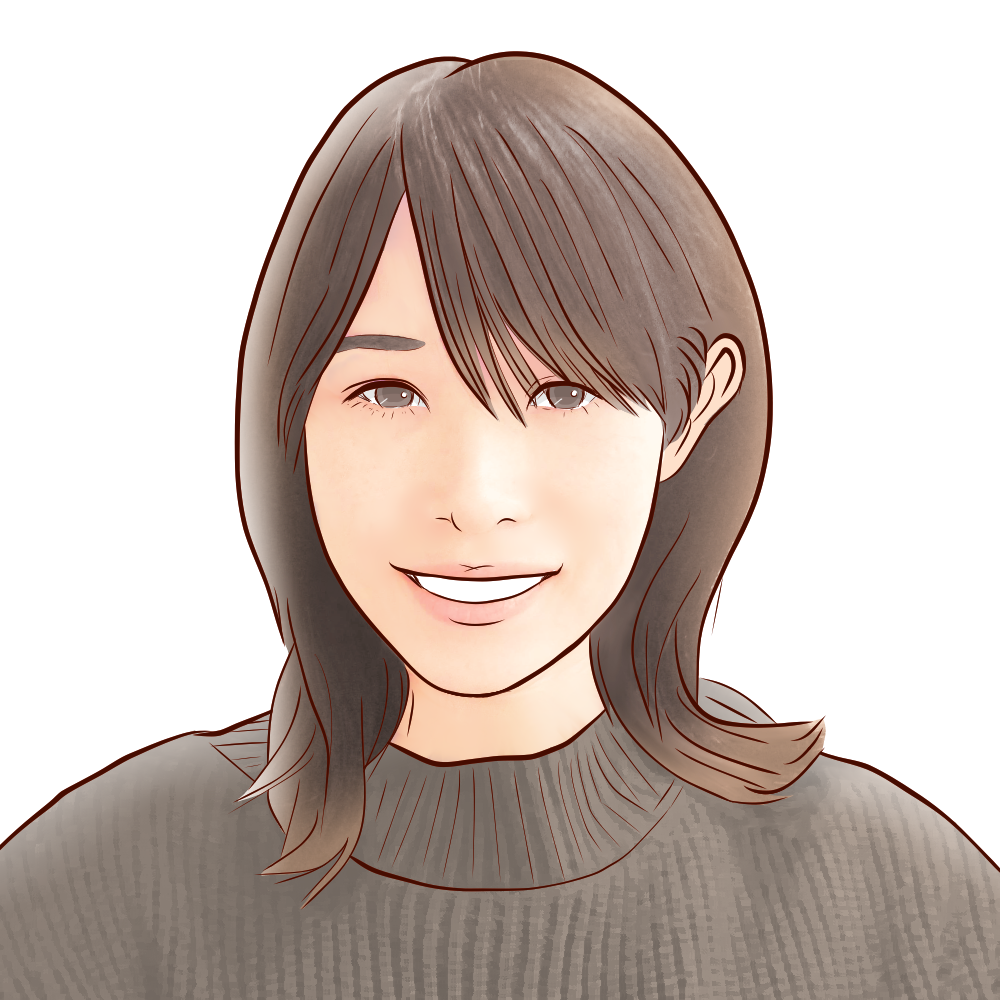
分析統括を担当しているさかいと申します。表題通り、受験3年目に突入しました。
「合格答案」を追及するふぞろいシリーズのブログにあって、今回は「多年度受験生」、つまり何度も不合格になっている現役受験生の記事、という一見するとコンセプトに反するような回なのですが、それにも関わらず今このページを見ている皆様はとても貴重な存在かもしれません。まずは最初に御礼を。ありがとうございます。
目次
自己紹介
【性別】女
【年齢】30代後半
【職業】行政機関勤務
【勉強法】1次:通信(STUDYing)
2次:ふぞろい+受験生支援団体での勉強会/事例Ⅳは30日完成と全知全ノウ
【受験回数】1次 :2回、2次: 2回
【得意科目】(1次):企業経営理論 (2次):特にない…
【苦手科目】(1次):財務会計、情シス、経済学 (2次):事例Ⅳ
【趣味】運動全般(走ったり殴ったり(!))、カラオケ、たまにサウナ
【自分をSWOTすると】S:謎に体力はある W:集中力がない O:まさに、ふぞろい執筆への関与 T:先読み不能な仕事量(いつも突然降って湧く)
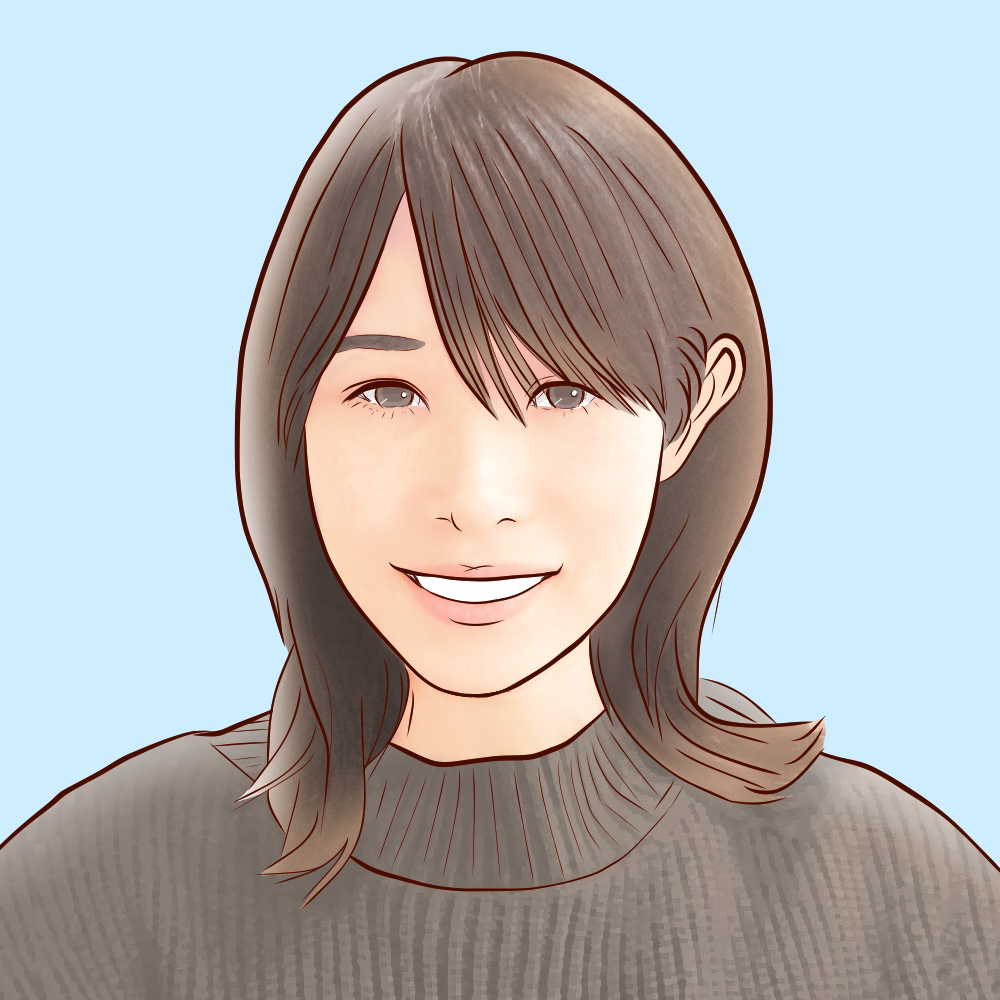
小学生の時からとにかく数字が苦手…
私が中小企業診断士試験を受験するワケ
このブログ記事が掲載されるのは4月4日。新年度が始まったばかりの出会いと別れのこの季節は、毎年のように、着慣れないスーツに袖を通した新社会人がとびきりのフレッシュさを携えて、職場の挨拶周りにやってくるものです。
そんな現場に遭遇する度、年々目がくらむようなまぶしさと共に隔世の感を覚えるようになった社会人歴十ウン年の私。気づけば妙な滞留感と物足りなさがそこにはありました。
単に1か所で長く勤務しているから?いやそれだけではないはず…。自問自答し、そこで私はようやく1つのことに気付きました。
1-2年おきの頻繁かつ畑違いの部署への異動も多いわが社の人事プロセスは、まさしくゼネラリスト量産マシーン。私も様々な業務に短サイクルで従事した結果、何でも一通りは無難にこなすけど、かといってこれだけは誰にも負けないという得意分野もない、まさに「何でもできるけど何にもできない」 人間となっていました。
今の仕事が嫌なわけではない、だけど、ただ流されるままに身を委ねていたら自分にはきっと何も残らないであろう。そこで生まれた「専門性への渇望」こそが、私を大きく突き動かしました。そして、興味があるのに勉強してこなかった経営や財務分野を学びたいと思い、どうせなら学歴か資格を、と欲も出し、最終的には診断士でも目指してみるか、という決断に至ります。
診断士は独占業務がないので専門性はさほど高くないのでは、という意見もあるかと思いますが、今まで培ってきたゼネラリスト的マルチさを素材として活かしつつ、少し専門性の味付けを効かせる事、この匙加減こそがむしろ私らしい方向性なのでは、と考えています。
「ふぞろい」に不合格者がいる意味とは~失敗の研究~
1次試験は労せず合格できたものの、なかなか2次試験の勘所をつかめないまま2年が経過。どうしたものかと思っているところに受験生メンバーとして参画する機会を得たのですが、まず悩んだのが、ふぞ執筆メンバーの中での自分の存在意義でした。
受験生は合格者のテクニックや思考、実際の合格答案を知りたいのであって、私の経験や勉強法はニーズがないのではないか。多年度受験生が何を語っても説得力もなければ参考にもならないのではないか。現役受験生としてのリアル目線という以上の付加価値を付けられる自信が正直ありませんでした。
そんな時、ひょんなことから目にした書籍がありました。
診断士受験界隈でも「SECIモデル」でおなじみの経営学者、野中郁次郎先生。その野中先生の共著である「失敗の本質」という本です。簡単にいうと、「なぜ失敗したのか」を組織論の見地から研究されたものなのですが、この本のタイトルを見た瞬間にある考えが浮かびました。―上手くいったことだけにフォーカスするのではなく、ダメだったこともきちんと向き合い反芻することで有用な1つのナレッジになるのではないか。皆があまり積極的に語りたがらないであろう「失敗談」ならむしろ説得力を持って語れるのではないか―
合格=成功、不合格=失敗という単純な図式ではない、との前提は理解しつつも、受験生としての自分の携わり方として、1つのヒントを得た気がしました。そんな訳で今後約1年、私個人としては「失敗から得た学びのナレッジ化」を切り口とした情報発信をできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
終わりに
次回4月7日(月)は、同じく受験生メンバーとして参加している「なかむー」の登場です。オンラインでも伝わってくるほど柔和な雰囲気を醸し出す彼は今、ブログで何を語るのか…?乞うご期待!