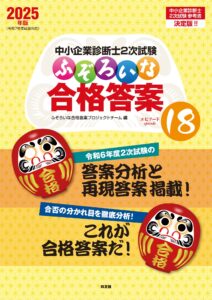自己紹介!もっさん編

こんにちは、もっさんです。ふぞろいな合格答案エピソード18では、事例Ⅱの分析と再現答案を担当しています。
さまざまな職業・年齢・志望理由・勉強法のメンバーが集まっているふぞろいメンバーの中では、主に平均年齢を引き上げる役割、副次的にはインターネットがなかった時代のライフスタイルについて語り継ぐ役割を担っております。
目次
自己紹介
【性別】男性
【年齢】52歳
【職業】デジタルマーケティングコンサルタント
【勉強法】1次:独学/2次:予備校(通信)
【受験回数】1次 1回、2次 2回
【得意科目】(1次):情報システム (2次):事例Ⅱ
【苦手科目】(1次):企業法務 (2次):事例Ⅳ
【趣味】パソコンゲーム、プラモデル製作(最近作ってない)、プロレス観戦(最近行っていない)
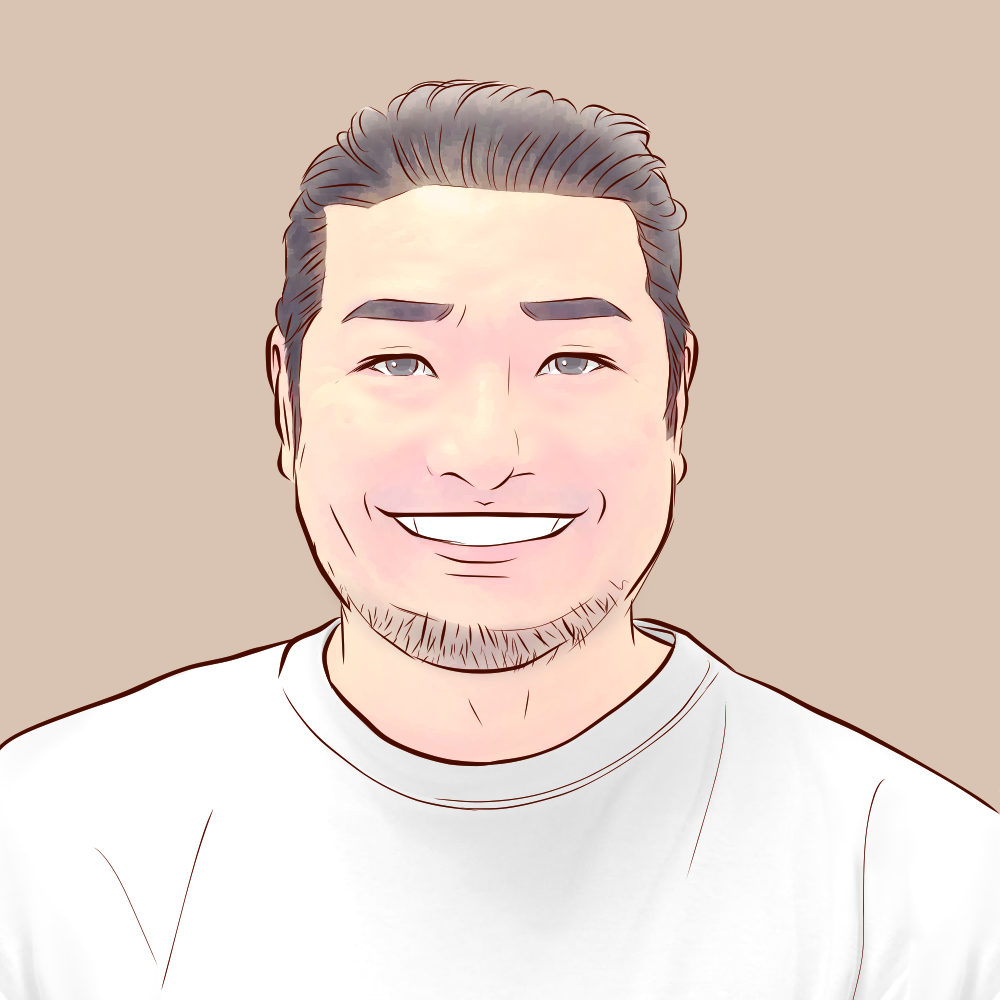
トップのイラストの使い方、大きすぎやしませんか?
中小企業診断士を受験した理由
私が中小企業診断士を受験することを決めたのは、2023年1月です。当時在職していた会社では、資格取得などの自己啓発への支援が手厚く、それまでに業務に関連したマーケティング関連の資格をいくつか受験していました。受験すると、なぜか理由はわからなかったのですが、ポコポコ受かるわけですね。(あ、ちなみに国家資格とかそんな大仰なものではなくて、○○検定というような、ライトな民間の資格です)。もちろん受験対策はしています。とはいえ中には難しいものもあったりして、同じタイミングで受験した同僚が合格できなかった……ということもありました。にもかかわらず私は連勝を重ねていたわけです。そこで私は、50年間気がつかなかった自分の隠された秘密に気がついてしまったのです。
自分には「ペーパーテストになると能力が1.5倍くらいになるバフ」がかかっているのではないか。そうに違いない。「バフ」とは、コンピュータゲームにおいて、攻撃力アップや防御力アップといったプレイヤーに有利な効果が付与されることです。おっさんなのでドラクエに例えますが、相手に与えるダメージが倍になる「バイキルト」などが有名です。
このバフ効果、この恩恵をなんとか生かせないものか。当時の私の悩みごとの一つに、残り10年を切ったサラリーマン生活をどのように締めくくるか、というものがありました。いや、締めくくるという表現はちょっと違うな。当時在職中の会社の定年は、60歳です。もちろん雇用延長や再雇用などの制度はあるのですが、それでも60歳が一つの区切りであることは間違いありません。でも年金の支給開始は65歳。60歳から65歳まで、どうやって収入を得るのか。10年後にやってくることが確実な「生活費をどうやって確保するか」という問題に対して、有効な解を持っていなかった、というのが適切な表現かもしれません。そしてその解に続く道を、「バフ効果を生かす」という選択肢が、キラキラと照らし出したわけです。
次にやるべきは、「じゃあどんなペーパーテストを受験するのか」を明らかにすることです。50歳から受験できて、これまでの自分のキャリアが生かせて、かつ生活費獲得という具体的な目的を達成できそうな資格はないものか。今ならAIに調べさせますが、当時はまだChatGPTが発表されて数か月しか立っておらず、検索AIもまだサービスインしていなかったため、人力でGoogle検索しました。
そこでたどり着いたのが「中小企業診断士」という資格です。名前は聞いたことがあるけれど、どんな内容なのかはそのとき初めて知りました。なるほど中小企業診断士なら、これまでの自分のキャリアも生かせそうだし、やることのイメージもなんとなくできる。挑戦したいという気持ちが湧いてきた。ところがそもそも司法試験とか公認会計士とか社会保険労務士とかだと、挑戦してみたいという気持ちすら湧いてこない。自分がその肩書で仕事するイメージが全く浮かばないな。その前に受かるイメージもない。
あと、現職はデジタルマーケティングコンサルタントということになっているのですが、「デジタルマーケティング」って、なんだか字面が軽いですよね。ふだんにこやかに接してくれているお客さんが、裏で「チャラチャラしやがって」と吐き捨てている可能性がないわけではない。ここに「中小企業診断士」の漢字7文字が加わると、そのあたりの軽さが中和されて、むしろズッシリとした重厚感が出るかもしれない、といったことも考えました。
以上を、中小企業診断士受験を決意した理由として50字にまとめると、「ペーパーテストを受験すると点数が20%増えるバフ効果の強みを生かして定年後の収入を確保するため。」です。
受験生活を振り返って
バフがかかっているため1年目で一次試験は通過できたのですが、二次試験で轟沈。それも「ぜったい受かった! 俺が受からずして誰が受かるのか!」という確信を得て受験を終えたところから、各予備校の模範解答を見るたびに鉛のように重い不安が増し、そして合格発表日、自分の受験番号が出てこない絶望の淵へのダイビングという沈みっぷりでした。あのときはキツかったなー。
2年目は、何がダメだったのかの振り返りと対策を実践して、時間をかけて仕上げましたが、「これなら大丈夫」と自信を持って受験した2回目の二次試験の事例Ⅳで頭が真っ白、解答用紙も一部真っ白というホワイトアウトから「足切りさえされなければワンチャンある」「ここでこそバフ効果」という細い細い糸にすがって獲得した合格でございますので、ひとことで申し上げますと、感情の起伏の山と谷をジェットコースターのように上下する2年間でした。
あまり受験にのめり込みすぎると、思ったような結果が出なかったときのダメージが大きくなるので、受験生の皆様に置かれましては、そのあたりのメンタル面においてのリスク分散的なことを念頭に受験対策をしていただきたいです。
でも、思いっきり全力出して挑んで結果が得られればとてもうれしいことだし、悲しいのは思いっきり全力出して挑んだ結果でもある。生きている実感は得られます。それは間違いない。
最後に
次はしゃろんの番です。そもそもなぜ「しゃろん」という名前なのか……。一つ言えるのは、「しゃろん」という言葉から、映画『氷の微笑』のイメージが脳裏に浮き上がってきた方がいらっしゃいましたら、すぐさま期待値のハードルを一番下まで下げていただいたほうがよいかも?ということでございます。よろしくお願いいたします。