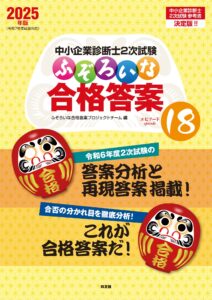2次試験対策いつ始める?勉強の仕方は?いっちー編
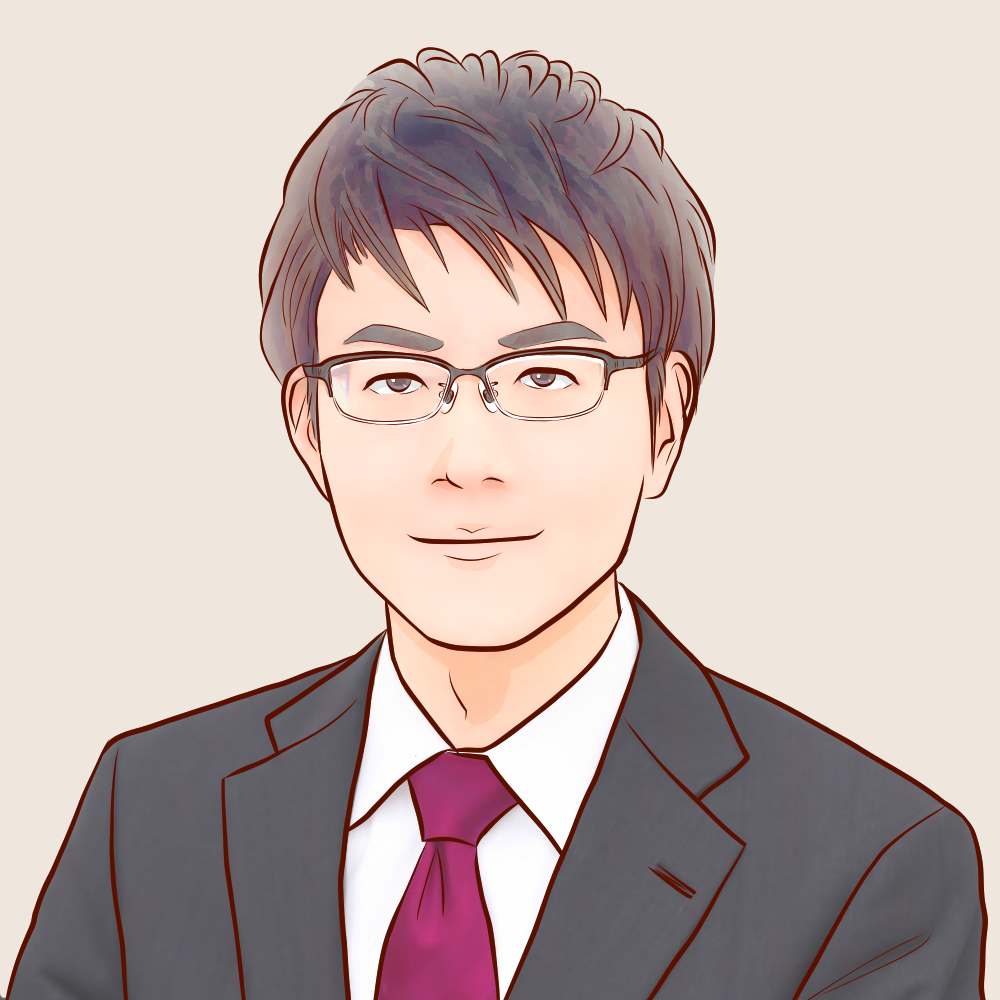
こんにちは、いっちーです。私は実務従事で診断士登録を行おうとちょこちょこコンサルをしていたのですが、ようやく15ポイント集まりました(まだ印鑑もらってませんが……)。実務補修の方々が既に登録を済ませてセミナーなどに参加しているのを見て羨ましいなあと思っています。
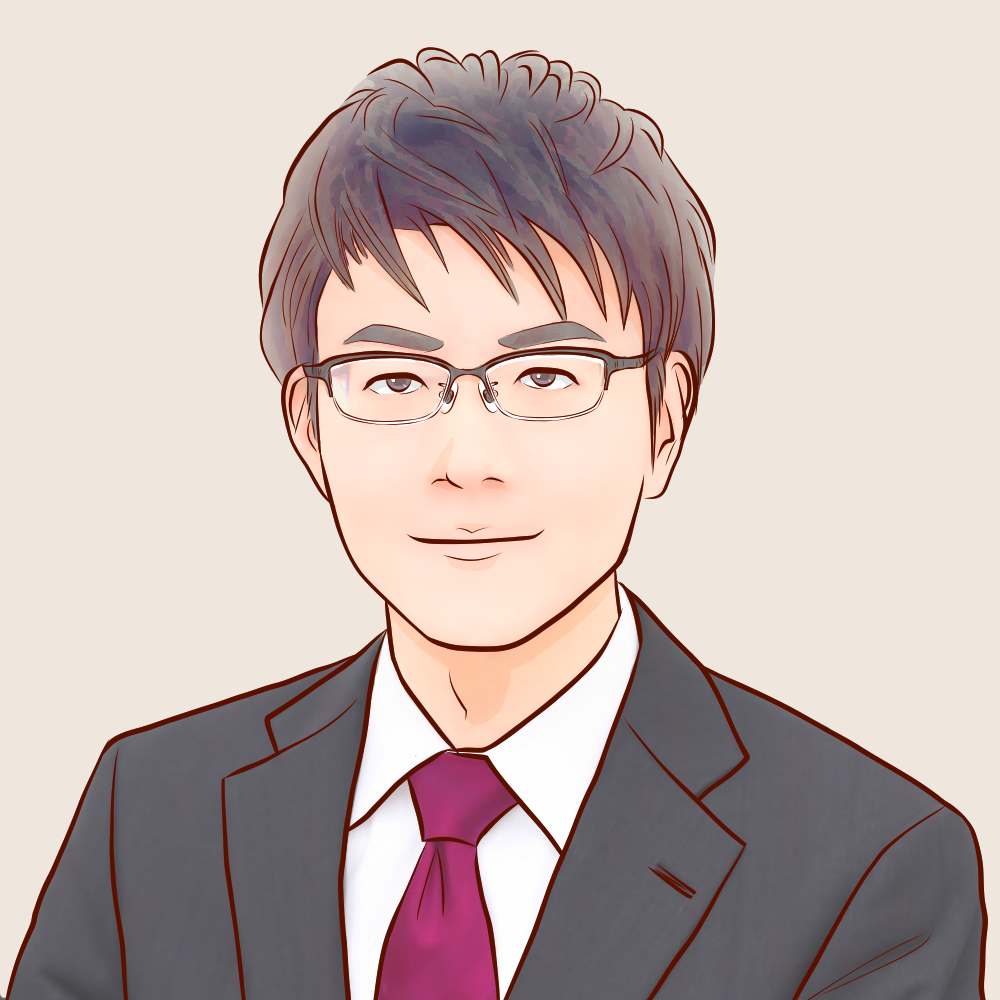
早く診断士登録したいです
さて今回は2次試験対策ということで、1次試験の準備でお忙しいところかとは思いますが、息抜き程度に読んでいただければと思います。最終的に2次試験も受けることになりますので、こんなもんなのねー程度に受け取ってもらえれば幸いです。
目次
(割と重要な)属性の確認
以前のブログから時間も経っておりますので、こちらで改めて背景について簡単に記載しておきます。私は公認会計士やらIPOの資格やら色々と持っておりまして、中小企業診断士試験の平均的な受験生と比べて前提知識に差があるかなと思っております。2次試験だけで言うと事例Ⅳの計算は公認会計士試験の管理会計論や経営学でかなりの分量を解いているので、その前提でご覧いただけると誤解がなく良いかと思います。また私は短期独学・ストレートでの合格となりますので、もしご参考になる方がいらっしゃれば嬉しいです。
2次試験対策を始めた時期
正直に言ってしまうと、1次試験の後、自己採点してから2週間後くらいです。
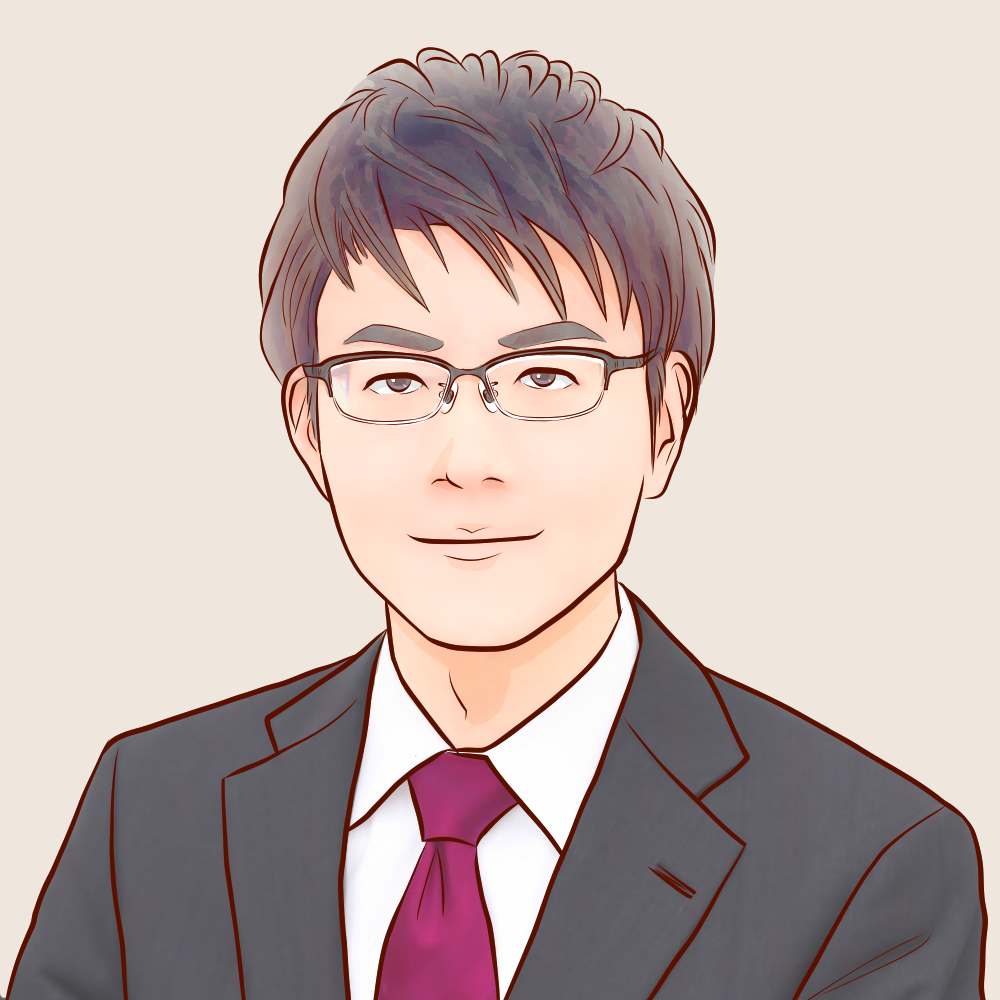
時期的にちょっと公私ともに忙しくて、受かった直後には勉強時間が取れませんでした。
最低限の準備として、試験形式の確認は直後にしました。
「4科目あるな」
「1次試験と被っている科目はこれか」
「じゃあ他の1次試験のテキストは本棚の奥に片してしまおう」
これくらいはやった記憶があります自室は本だらけなので、定期的に棚卸が必要なのです。
理想としては1次試験の勉強中に2次試験の対策も踏まえながらやることが良いのでしょうが、あまり現実的ではない気がします。理由としては、要求されるスキルが違いすぎるからです。1次試験は余裕すぎて早く試験日が来ないかなという感じの人以外は独学ストレートだと難しいと思いました。
勉強法について
それから勉強を開始しましたが、使った教材は『ふぞろい』1年分と協会が出している過去問題、そして1次試験のスピードテキストです。とにかく時間のない私、過去問演習で実際に手を動かしたのは1回だけ。じゃあ他に何やってたのかという話を書いていきます。
過去問を見てみると分かるんですが、設定は違えど事例ⅠからⅣっておおよそパターンが決まっているんですね。多少は時事ネタ(例えば新型コロナや事業承継ネタなどあります)が影響しますが、試験範囲が変わらないので答えるべき内容自体にはそんなに大差がないです。皆さんは中小企業庁出題の要旨とか読んだことありますか? あれを読むと何を読み取り何を記載することが要求されているかが分かります。私はあれらを丁寧に問題と突き合わせて読みました。また事例文を掘り下げてみたところ、それぞれの事例ごとに共通している流れというか、使える経営資源だとか、その辺りが見えてきました。
前回のブログでたくも触れているので重複するところがありますが、A社の時系列は割と長く(半世紀くらい)、十年くらい前まではいい感じでした。しかし外部環境/内部環境の変化についていけず(もしくは策を講じるも上手くいかず)、経営が低迷してしまいました。困ったA社に後継ぎ(もしくは次期経営者候補)が何らかA社になかった強みを持って帰ってきました(もしくは外部環境がA社にとって有利な気配を匂わせてきました)。とおおよそこんな流れです。使える経営資源は割と本文に明示されており、網羅的に拾ったりまとめたりが難しい。時系列が長いので、設問中どこを問われているのがによって解答が大きく異なってくるので時制注意。とまあこういうことをノートに書いていきました。
書いていくときりがないのですが、例えばB社は使える経営資源がほぼ無い(少なくともカネはない)ので、代々受け継がれてきた「何か」や「繋がり」が強みになるケースが一般的で、何か施策を行う際は地域創成と絡めて地域や周辺の力を借りた企画を考える。C社は大体QCDのうちQは高い(使える経営資源になる)が、外部環境の変化によってCやDに問題が出てきたのでどうにかしなくてはならないみたいな状況に陥っている、というように整理が可能です。なおD社は計算問題主体なので割愛します。
一方で訊かれることは様々です。与件文に沿って解答を組み立てますが、前提知識がないと全く解けない問題もあります。そこで1次試験のスピードテキストです。関連するキーワードを頭に定着させて、切れる手札を増やす作業に専念しました。この作業でキャンパスノートがちょうど1冊使い終わりました。タブレットなどで勉強されている方も多いかと思いますが、私はプログラミングが関わるもの以外は全て紙とボールペンのアナログ人間です。最後に過去問を80分で解いてふぞろいで採点して試験に挑みました。
事例Ⅳについて
これは私が助言するのが難しいところではありますが、皆が取れるところは必ず取れ、取れなさそうなところも何かしら埋めろに集約されますかね。利益率や回転率などの絶対落としてはいけないところは必ず合わせて、例えばNPVとリアルオプション、ターミナルバリューが絡むような複雑な計算でもイレギュラーの無い年のFCFや少なくとも減価償却費は計算できるかと思います。白紙というのはどう採点者が下駄を履かせようとしても0点にしかなりません。しかし嘘ではない何かが書かれていれば手心を加えてくれる余地は残ります。会計士試験でもそうなのですが、割と白紙答案ってあるんですよ。ほんとに。分かり得ることを何か書くんだ、あがいてみせろと思います。
ちょっとシリアスなこと言うと、戦略的ではない(ほかに時間をかけると決めた時に生じるもの以外の)白紙答案はお手上げ状態ということになります。診断士としてクライアントと接するとして、全く分からないことを聞かれた際に黙り込んで答えないってあり得ませんよね。これは他の事例にも当てはまりますが、解答用紙は採点者との唯一のコミュニケーションツールです。コンサル実務的には持ち帰って後ほど答えることにはなりますが、その場でも一般的に言えることは何とか答えようとするはずです。それを解答用紙でもやりましょうよという話でした。
終わりに
軽く書くつもりが長くなってしまいました。次回は養成課程に通いながらも2次試験の勉強をしている「ぴろ」です! 現役で勉強を続けている彼の学習方法に乞うご期待!