A社ベタストーリー(この物語は全てフィクションです)

目次
はじめに
おはようございます。山は取るものではなく登るもの・Tommyです。昨日のしののみほ送りから割り込んでしまいました。期待された方、申し訳ございません。
さて、正規のブログリレートラックを外れまして、パラレルな感じでちょっとした連載を進めたいと思います。
この度、中小企業診断士試験にありがちなストーリーを妄想し、更に試験とはまるで関係が無いけれど「どっかで見たことあるな」と思うような「平成のベタ」をちりばめて、架空のA~C社のお話を創作してみました。
こんなお悪戯ですが少しでも皆様の勉強にもなるよう、知識で穴埋めできそうなことを台詞形式にしています。もし良ければそこにどんな台詞が入るか、あらゆる可能性を考えてみてください。
それでは、どうぞ。
(参考文献:「新明快!困ったときのベタ辞典」大和書房)
======★★====================================
ふぞろい16メンバーのブログは2月20日スタート!
どうぞお楽しみに!
===============================★============
第1話
20XX年8月。暑い暑い夏の日だった。若き中小企業診断士・高山龍治は中国地方のX市にある古くからの商店街に立っていた。絞れるほどに汗をかいたYシャツの腕は捲っている。ビジュアル的観点から、龍治は半袖のYシャツを着ない。タンクトップなんてもっての外である。クールビズに従うのはノーネクタイのみというのが彼の信条だった。
地図アプリが示すとおりに真っ直ぐ歩くと、商店街の端に小さな店構えの和菓子屋があった。芳ばしい香りが漂っている。ここが今回お悩みを抱えるA社だ。龍治は店の前で少しだけ息を吐くと、年季の入った暖簾をくぐった。
「いらっしゃいませ」
和菓子屋らしく浴衣を着た若い女性の店員が挨拶をする。決して不愛想なわけではないのに、何となく雰囲気が暗い。すっかり自分を客だと思い込んでいる彼女に丁寧に自己紹介をすると、少し意外な表情をしながらも奥の応接室へと通してくれた。
空室でもきちんと準備されたエアコンの冷気を感じながら龍治がお礼を言うと、彼女は小さく会釈をしてその場を去ろうとした。その時だ。
「ちょっと、お店に誰もおらん思うたら、あんたがサボっとったけぇね」
浴衣ではなく、ウエイトレス風の淡いブルーの制服を着た別の女性が、持ち場へ戻ろうとする店員の前を大胆に遮る。冷気を感じたのはエアコンのせいだけではなかったようだ。
「す、すみません…今戻りますけぇ」
立ちはだかる女性の脇を縫うようにして、浴衣の女性は持ち場へと戻っていった。すぐに洋服の女性も奥へはける。数秒後、奥の部屋からは数名の女性たちの嘲笑するような笑い声が聞こえた。
「ちょっと、見られたくないもんを見られちまったようじゃね」
龍治が気付かぬ間に、A社の代表取締役・相川賢二が立っていた。バツの悪そうな笑顔で頭を下げると、賢二は龍治に着席を促し、A社の歴史について語り始めた。龍治は事前に調べておいた情報と重ねながらそれを聞く。
「要するに、今起きとるんは派閥闘争みたいなもんやけぇの」
この地に菓子店を開いたのは賢二の父・賢一だった。戦後の混乱期、少ない食材を駆使しておはぎを売り歩いたのが始まりだ。しばらくして物資が安定的に供給されるようになると、賢一は他社に先駆けて味へのこだわりを追求するようになった。その試行錯誤が功を奏し、地元ではちょっとした有名店となる。後に市内有数の商店街となっていくこの地に店を構えたのも、先見の明があったのかもしれない。堅実だった賢一は大きく店舗網を拡大するでもなく、自分の目の届く範囲での商売を心掛け、利益も着実に積み重ねていった。
その賢一が亡くなり、今目の前にいる賢二が社長を引き継いだのは30年ほど前のことだ。日本経済はバブルの頂点へと向かっている時期。引き継いだ賢二は和菓子職人としてよりも経営の方に興味を持った。自分は製造から手を引き、これまで手作業で行っていた工程を機械化。大量生産を可能にして店舗の拡大も図っていった。また、その間、廃業寸前だった小さな和菓子店をいくつか買収し、その職人を受け入れてもいる。それぞれが個性を持つ職人を統括するのは難しく、離れていく者も多かったという。
事業は拡大の一途をたどったが、それに遅れて、消費者の心はじわじわと離れていった。
「それって…」
龍治が言おうとして憚られた言葉を賢二が継ぐ。
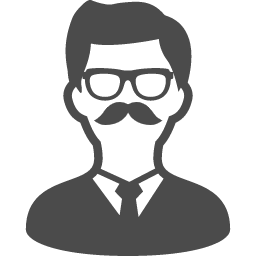
そう、○○○○が理由じゃろうな。
賢二は視線を落とした。反省点は充分に理解し、悔やんでもいるようだった。話は続く。
バブルは崩壊し、日本全体が不況に不安を募らせている間、A社の転落も早かった。一時期は中国地方の全てに店舗を置いたものの、続々と撤退。結局はこの本店だけが残ることとなる。
更にA社にとって脅威となったのが、北関東に本店を置く安価な菓子店S社の急成長である。S社は和洋どちらの菓子も販売し、価格の割には質も良く、何より目新しさがある。最初は賢二も「関東圏だけの話だろう」と考えていたが、その破竹の勢いは全国に及び、あっという間に中国地方まで到達していたのだ。
いつの時代も、オセロの色が変わるのはあっという間である。A社の経営は以前よりも加速をつけて悪くなっていった。
そんな時にS社の担当者から持ちかけられたのが、S社への子会社化だった。賢二は迷った。A社は賢一が人生をかけて作り上げた資産である。勢いが衰えたとはいえ、今でも地元の人たちに「A社」と言えば知らないものはいない。それが新興菓子店の傘下に入ることは、父の努力を無下にするようで苦しかった。
悩みぬいた挙句、賢二はある交渉をした。それは、子会社化しても店舗名はA社のまま、S社の製品と併せてA社の製品の一部も売り続けるということだった。S社は意外にもそのあっさりと受け入れた。
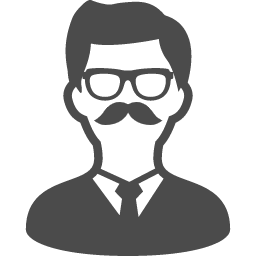
結局、S社もウチの○○○○は欲しかったんじゃ
S社との合併により、A社は破産の危機だけは免れた。しかし苦境は続く。それが先ほどのすれ違いざまの社員の諍いと、賢二の言葉なのだ。
「基本、S社は工場で集中して製造したものを店舗に送るシステムなんじゃけんど、ウチは経営が良かったときに投資した設備があったけぇね、一部S社の商品を店舗で製造することにしたんや。じゃけぇS社からも職人と店舗スタッフが派遣されたんよ。ほんならやっぱりというかなかなか融和が進まなんで…なんやS社も弊社への派遣は子会社出向という扱いじゃやったもんで、あっちの社員の方にも不満があったんじゃろうけどねぇ」
「よくある話だ」と龍治は心の中で思う。あまりにもありがちな老舗中小企業の遍歴だ。
龍治が氷の溶けた冷茶をすすったとき、応接室の扉が開いた。
「遅くなってすまんの。おぅ、こちらが診断士の先生か。ボンジュール、いや、こんにちは」
南欧でバカンスでも取っていたような半袖シャツにハーフパンツの若い男が龍治に向かって手を差し出した。龍治も反射的に右手を出す。
「弊社の次期社長、相川賢三です。今はあっちでパン屋みたいなのやってますけど」
「ん?」といった顔で龍治は賢二の方に目をやった。賢二の顔が更に曇っている。
「あ、食べます?僕が作った『あんこマリトッツォ』。僕ね、今これ一本でやってんです。全国唯一のあんこマリトッツォ専門店!」
賢三が手にした袋からあんこマリトッツォなるものを取り出す。店に入るときに甘い香りがしたのは、A社からではなく、向かいにあるこの三代目の店からだったようだ。
「僕はね、このあんこマリトッツォの可能性に賭けてるんですよ。僕もフランスでしばらくパンの修行したんですけどね、やっぱ日本とヨーロッパじゃ菓子のレベルが違う。現地の職人さんとも今コンタクトをとってて、いずれは世界進出かなって」
龍治の舌にとろけるように甘く、ひんやりした生クリームとあんこが乗ったが、心なしかざらついていたように感じた。
都内のいつもの居酒屋に着くと、有賀実果は既にほろ酔いだった。
「りょーぉち!遅いよ!全くもう!」
「だからさ、その呼び方はやめろって」
実果は面白がって未だに龍治が受験生支援団体で使っていたハンドルネームで呼ぶ。実果はそのセミナーに受験生として参加しており、偶然ブレイクルームが数回重なることで親しくなった。結局実果はその年、仕事の都合で受験勉強を中断したが、今年は一次試験を無事通過し、二次試験を控えている。そうやって知り合ってもう3年だ。いくら彼女が日本最大の機械メーカー・日の丸工業で働き、都会のOL生活を満喫しているように見えても、曖昧な関係を続けるには限度がある。それでもどこか彼女の試験が終わるまでは…とチェックメイトを引き延ばしにしている節があることを、龍治自身が気付いていた。
「そもそもさ、何で和菓子屋の息子がフランスにパン修行に行って結果マリトッツォなわけ?あれってイタリアのお菓子でしょ」
「あ、そうなんだ。まぁなんか…色々間違ってるよな」
龍治はそう答えるのが精いっぱいだ。
「そもそも賢三さんに新たなお店を出店させるって、どういうことなのかしら」

○○○○という意図があるんじゃないかな。
「そっか、なるほどね。さっすが診断士じゃない!」
実果が勢いよく龍治の肩を叩く。
「社長さんはさ、結局どうしたいんだろうね」
実果の言葉に、龍治は先日の面談での賢二の顔を思い出した。
≪続く≫











