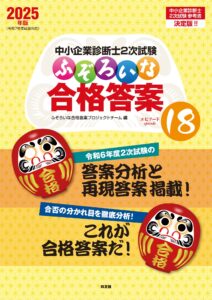「世界標準の経営理論」を読み始めてみたPart 2(センスメイキング理論)

みなさん、こんにちは。オールドルーキーの心の友、くろひょうです。
新年早々始まる全豪オープンが楽しみで仕方ない今日この頃ですが、2次筆記試験の発表も近くなり、そわそわする時期ですね。私も発表1週間前くらいは神社の近くに寄る度に神頼みをしていました。
さて、昨年の6月に「『世界標準の経営理論』を読み始めてみた」という記事を書いた後、全く本件に触れてないのは、ご察しの通り読書が進んでなかったということなのですが、12月に著者の入山章栄教授の講演を聴く機会があり、その際にも「センスメイキング理論」について触れていましたので、そこだけは先に読み、今回のブログの記事とする決意を致しました。
先のブログにも記載したのですが、企業診断2020年1月号における入山教授へのインタビュー記事では「センスメイキング理論は中小企業診断士の武器になる」とのコメントがありました。数多くの経営者やビジネスパーソンと交流してきた入山教授は「現在の日本の大手・中堅企業に最も欠けており、最も必要なのがセンスメイキング理論と考えているといいます。一体、どのような理論なのでしょうか。
目次
センスメイキング理論とは
センスメイキング理論は、本著では第3部「ミクロ心理学ディシプリンの経営理論」としてカテゴライズされています。
センスメイキングはいまだ発展中で、その定義自体も多様だ。しかし筆者の理解では、その本質をよくとらえた日本語がある。それは「納得」であり、さらに平たく表現すれば「腹落ち」である。センスメイキング理論は、「腹落ち」の理論なのだ。より厳密には、「組織のメンバーや周囲のステークホルダーが、事象の意味について納得(腹落ち)し、それを集約させるプロセスをとらえる理論」と考えていただきたい。
(P417)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
なるほど。。。最近、若手が計画会議のブレストで「腹落ちしない」と繰り返していたことを思い出しました。「腹落ち」という言葉をここ数年で急によく聞くようになったのは、センスメイキング理論が広まっていることもあるのでしょうか?おっさんも、ちゃんと時代についていかなければいけないですね。
哲学的背景
本書では「現実は一つか」という哲学について触れています。
・実証主義=「客観的に、正確に分析した実証結果は、誰にでも共有できる普遍的な真理・真実である」
・相対主義=「物の見方・認識は、主体と客体の相互依存関係の上で成立する」
実証主義的に考えると、「自分が直面しているビジネス環境は周りのみんなも同じように見ているはずなので、事業環境を正確に分析すれば普遍的な真理が得られる」となります。理想ではあるかもしれませんが、そんなことはなさそうですね。
一方で相対主義的の立場を取るなら、そこには誰もが共有する「絶対的なビジネス環境の真理」はない。さらに、主体は客体(環境)の一部と考えるから、皆さん自身が行動して環境へ働きかければ、環境認識も変化していく。
(P420)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
センスメイキング理論は、認識論的相対主義に近い立場での理論とのことです。私は納得感がありました。同じ会社の比較的認識が近い同僚と話をしていても、ビジネス環境を同じように見ているとは思えないですし、私自身の認識もどんどん変化していきます。
話が飛びますが、執筆案件で、コミュニケーションに関する取材をした際に、「コミュニケーションは絶望から始まる」「実はあなたの隣に座っている人は、あなたが当たり前だと思っていることをまったく当たり前だと思っていないのが現実」と言われたことをふと思い出しました。みんなが同じように見えていることはないから、腹落ちできるように働きかけをすることがとても重要なのだと理解しました。
全体像
主体(自身・自身のいる組織)と客体(周囲の環境)の関連性について循環するプロセスとしてとらえられ、プロセスは①環境の感知 ②解釈・意味づけ ③行動・行為に分けられます。
①環境の感知
当理論は、「新しかったり、予期しなかったり、混乱的だったり、先行きが見通しにくい環境下で、重要になる」と主張してます。まさに、VUCAの時代に重要な理論ということですね。危機的な状況(コロナ禍、急速な技術変化など)、アイデンティティへの脅威(自社の事業や強みが陳腐化する等)、意図的な変化(意図的に戦略転換を行う時など)、いずれもが日本企業が現在直面し、今後も直面する可能性が高いことですね。
そしてこの急激な変化の中では、企業自身が意図的に変化し、イノベーションを創出しなければ生き残れない(=intended change)。しかし一方で、「そもそもこの会社の存在意義は何か」が揺らいでいるために、自社の大きな方向性に腹落ちがなく、結果として変化ができない企業は実に多い(=threat to identity)。
(P422)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
②解釈を揃える
相対主義を前提とする当理論では、同じ環境でも、周囲の環境をどう解釈するかで意味合いは人によって異なる。そして、先行きが見通しにくい環境下で、より解釈の違いが顕著になり、なおさら解釈の足並みを揃えることが重要だと言います。
・・・組織・リーダーに求められるのは、多様な解釈の中から特定のものを選別し(selection)、それを意味づけ、周囲にそれを理解させ、納得・腹落ち(sensemaking)してもらい、組織全体での解釈の方向性を揃えることなのだ。ここで重要な力が、納得性(plausibility)である。
(P423)
通常、事業環境分析で重要視されがちなのは、客観的な情報と、それに基づいた正確な分析である。しかしこれは、「この世には客観的な一つの真実がある」という実証主義を前提にするから、可能な話だ。しかし、急激に変化し、いままでの経験が通用しない、解釈が多義的になる環境では、そもそも正確な分析が不可能だ。仮に正確な分析をしても、相手を納得させることもできない。逆に求められるのは、「現状はどうなっているのか」「我々は何をすべきか」についておおまかな方向性だけを示し、それに意味を与え、説得性のある言葉で周囲に語りかけて納得してもらい、足並みを揃えることになるのだ。
すなわち、「ストーリー性」がまさに重要なのだ。その学術的な背景は、センスメイキング理論にある。
(P424)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
確かに、SWOTや5フォース分析を同じ部内で行っても、考えがバラバラで、みんなが納得する正確な分析なんてできないと感じることも多いです。正確な分析をして相手を納得させることは無理があるというのは私もよく感じていることでした。著者は、「求められるのは、ストーリーを語り、腹落ちさせられるリーダー」だと言います。
③行動・行為
相対主義では、主体は客体と分離できないから、組織は行動して環境に働きかけることで、環境への認識を変えることができると考えられるため、「行動」が重要になるということです。
多義的な世界では、「何となくの方向性」でまず行動を起こし、環境に働きかけることで、新しい情報を感知する必要がある。そうすれば、その認識された環境に関する解釈の足並みをさらに揃えることができる。このように、環境に行動をもって働きかけることを、イナクトメント(enactment)という。
(P427)
イナクトメントしなければ環境は変わらないし、センスメイキングもできない。まずは行動をすることで、人はさらにセンスメイキングを続けられるのだ。
(P427)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
著者は、森の入り口の前で森の中の状況を推測するよりも、実際に飛び込んで、道に迷ったり、熊に遭遇したりしなければ、センスメイキングできないという例え話で説明してましたが、若手の頃に営業の心得として「とりあえず竹やりでも持って、戦場に出て、弾に打たれたら戻ってきてまた考えたらいい」というようなことを言われたことを思い出して笑ってしまいました。無謀に飛び出して深い傷を負った気もしますが、「行動」ありきで動いたことでセンスメイキングしていたのは確かかもしれません。。。
本書ではホンダが戦略なしに米国に進出してイナクトメントして成功した事例や、軍の偵察部隊が雪山で猛吹雪に見舞われた際に、間違った地図を見つけ、助かると思い込んだことで下山できてしまった例が書かれています。センスメイキングがあるから危機を乗り越えられたというのです。
すなわち、冷静で客観的だったら不可能だったことを、「思い込む」ことで実現してしまったのだ。このように、「大まかな意思・方向性を持ち、それを信じて進むことで、客観的に見れば起きえないはずのことを起こす力が、人にはある」というのがセンスメイキングのもう一つの大きな命題である。これを、セルフ・フルフィリング(self-fulfilling:自己成就)という。
(P429)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
セルフ・フルフィリングは「認知バイアス」の一つとして、多くの研究があるとのことで、「石油ショックによる日本のトイレットペーパー不足」や、「銀行の取り付け騒ぎ」なども、このメカニズムで説明できるとのことです。
必要なこと「未来は本当に生み出せる」
これらをビジネスに置き換えた時、優れた経営者やリーダーとして必要なのは、「未来へのストーリーを語り、周囲をセンスメイクさせ、足並みを揃え、環境に働きかけて、まずは行動すること」だと著者は主張します。
孫氏にしても永守氏にしても、イーロン・マスク氏にしても、いま「未来をつくっている」経営者たちが、ストーリーで物事を語るのは偶然ではない。未来を生み出すためには、ストーリーで周囲をセンスメイクさせることが必要なのだ。そうすれば、事前には「ありえない」と思われていたことが、事後的には「ありえる」のである。未来はつくり出せるのだ。
これは妄言でも、精神論でもない。カール・ワイクという既に齢80歳を超える希代の組織心理学者が長い間訴え続けてきたことであり、いま多くの経営学者が支持する、世界標準の経営理論なのである。
(P432)
引用:入山章栄著『世界標準の経営理論』
アナリストや投資家も、最終的な投資判断は、その会社・経営者に納得できるストーリーがあるかないかで決める人は多いと言います。確かにそうかもしれません。「ビジョンが重要」と診断士試験でも口酸っぱく言われるのも納得です。
入山教授の講演
ちなみに、12月に聞いた講演はDX戦略のテーマだったのですが、下記のような話がありました。
- 「知の探索×知の深化」の両利きの経営が重要。日本は特に「知の深化」に偏りすぎのパターンが多いから、知の探索をすべき、そして、ここは儲かりそうだと思ったら深掘りしよう。
- 知の探索は人でないとできない。知の深化はRPA、AIで代替できる。
- 頑張って効率化できると、知の探索の時間も増やせる。
知の探索・知の深化理論も本著に掲載されており、「イノベーションを説明する際に最重要視される理論」とのことです。ここ数年、「新結合」や「オープンイノベーション」等の言葉を社内外で頻繁に聞くようになったり、スタートアップに出向させる等の動きが急に活発になったなあと思ったのは気のせいではなかったわけですね。さらっとしか読めてませんが、「知の探索」はまず小さな仕掛けから行い、それを繰り返して、探索に慣れることから始めるのが重要とのことです(例えば、帰りの降りる駅を一つ変えるなど)。
そういえば、最近は大阪で常に新しいカレー屋を探しているし、昔みたいに「天下一品」ばかりではなく、他のラーメン屋も探索しているし、「私も知の探索の第一歩を踏んでいるぞ!」とちょっと嬉しく思いました(違うか。。。)。
明日は、今年に入ってさらにエンジン全開のたまちゃんです。お楽しみに!