この時期何やってた?やーみん編(答:診断士ゼミナール)

こんにちは!やーみんです。
季節はもうすっかり春、そしていつのまにか年度末ですね。
弱小製造業(資本金3億円以下ってやつです)の弊社でもこまごまとした組織再編が行われまして、
やーみんくん、成績が芳しくないから、4月から開発に異動ね

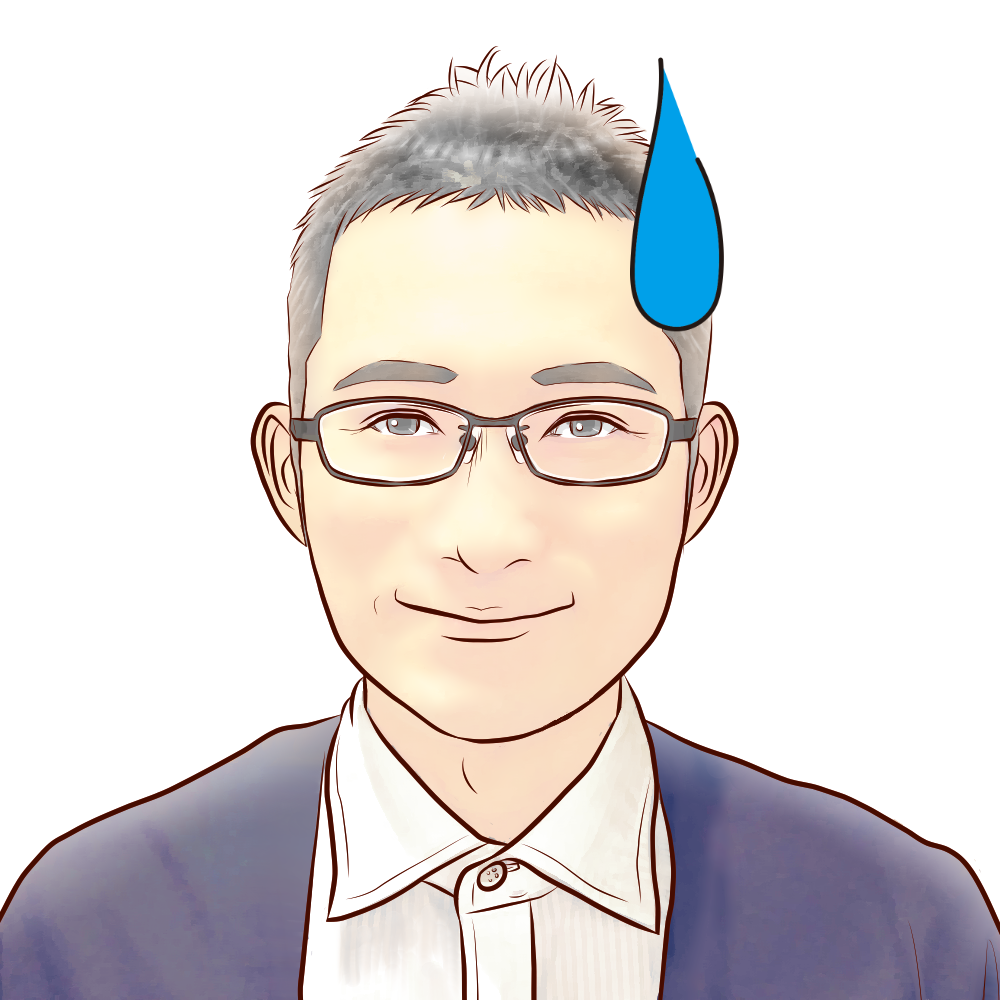
えええっ、私、現場と試作しかやったことないんですけど…
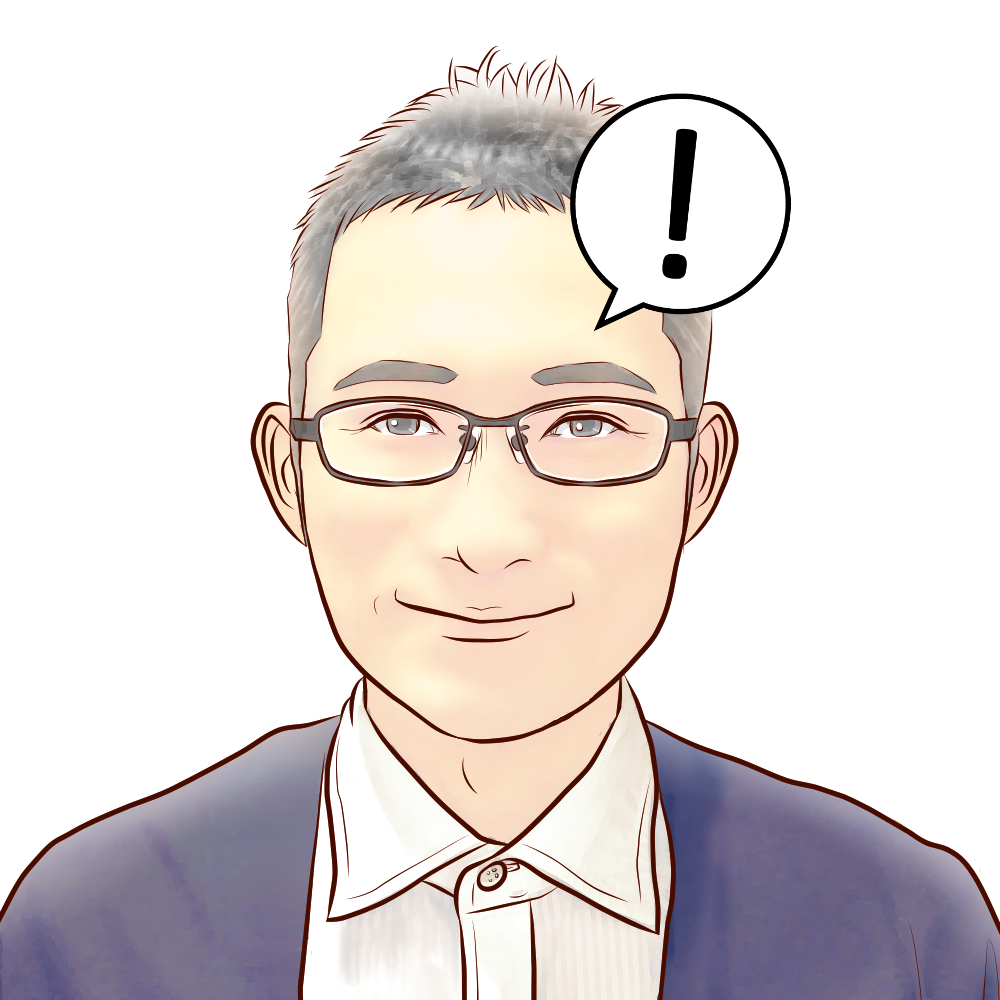
いや、でも話聞くと、結構重要そうなテーマ任せてもらってるんじゃね?
ちょっと気合い入れて、勉強してみますか!!
といった感じで、不安7割楽しみ3割くらいで過ごしています。
読者の皆さんの周りにも、大小さまざまな変化が起こっているのではないでしょうか。
そして!
新しい一年が始まるということは、新たな挑戦を始めるチャンスでもあります。
診断士の勉強を始めたばかり、または踏ん切りがつかない、というあなたに向けて。
約5か月の学習で1次試験に突入し、511点をもぎ取ってきたやーみんが、
この時期何をやっていたか、少しお話させていただきます。
目次
何やってた? ⇒答え:診断士ゼミナール

この時期、私は学習開始後、約1か月。
診断士ゼミナールの講義を倍速視聴し、ひたすらインプットする日々でした。
その進捗は、経営法務、経営情報システムが一通り完了、企業経営理論が7割といったところ。
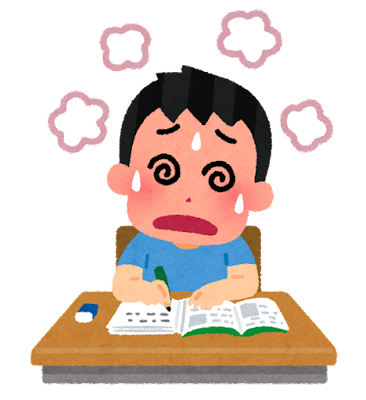
まだ2科目しかゴールしてないし、手つかずの科目がまだ4つもあるの?
お、終わんねー……
となっていたことを覚えています。
さて、なぜ診断士ゼミナールを、ひいては通信教育を選択したのか。
理由は大きく3つあります。
理由①:退路を断つため

これが、最も大きな理由になります。
診断士ゼミナールの受講料はおよそ5万円、テキスト代も含むとおよそ7万5千円。
通学の教室に通っている方からすれば、寧ろ割安なのかもしれませんが、
少なくとも当時の私にとっては、気軽に投入できる金額ではありませんでした。
それでも、受かる保証もない難関資格に大金を投入するということ。
それは、妻を説得する工程も含めて、
「断固たる決意」を固めるために必要な儀式だったと思います。
これだけのお金を払っちゃったら、もうゲームしたりマンガ読んでる場合じゃないですよね。
実際、二次試験を受験するまでの約8か月、「しんどいなあ」「今日は勉強できないなあ」
となったとき、思い出すのは、
大金を振り込むときの震える気持ちと、夫のワガママを許してくれた妻への感謝の気持ちでした。
理由②:学習時間をショートカットするため

中小企業診断士の勉強時間は、一般に約1000時間とも言われます。
(自分を振り返っても、周りを見渡してみても、全くあてにならない数字だとは感じていますが…)
子持ち仕事持ちの状況で、真っ当にこの時間を消費したくない気持ちがありました。
そのため、効率よく勉強するために、通信教育の力を借りることにしました。
いわゆる「お金で時間を買う」という感覚です。
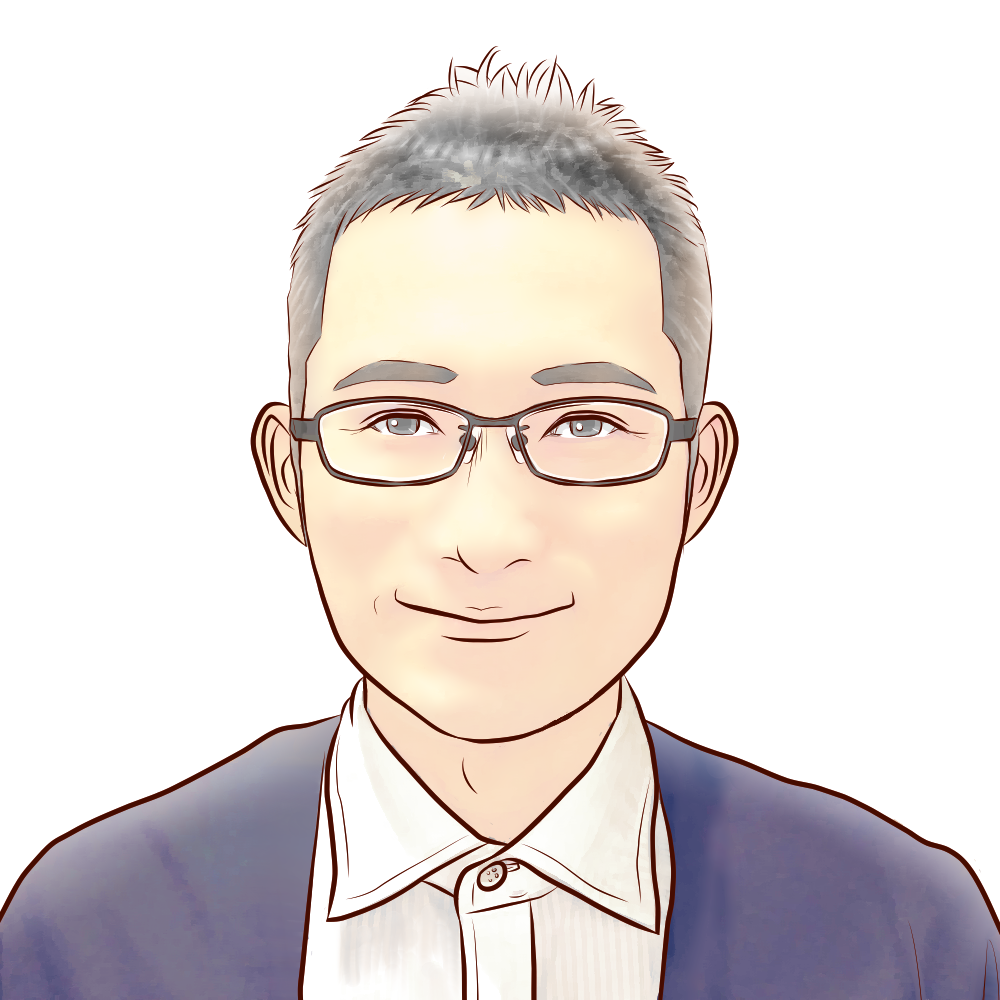
効果は抜群でした。
診断士ゼミナールはスライドを使った講義となっていますが、重要論点はすべて口頭でも説明されるため、
耳だけで聞いてもある程度追いかけることができます。
また、VLC media playerというソフトを使用することで、倍速、3倍速で講義を再生することができます。
これにより、移動や休憩などの隙間時間は耳だけで講義を追いかけ、
帰宅後はPCにて2~3倍速で視聴することで、効率よくインプットを行うことができました。
※余談ですけど、診断士の総勉強時間、よく聞かれるんですけど、よく分からないんですよね。。
耳だけで講義を聞いてた時間をそのまま算入する事には抵抗があるし、
ベッドで参考書を読みながら寝落ちした時間も数えられない。。
理由③:多年度を見据えた教材選択

これは、診断士ゼミナールを選んだ理由、ということにもなるのですが、
他の通信講座と比べた時、「3年間受講延長無料制度」というのが非常に魅力的でした。
これは何かといいますと、もしその年に不合格だった場合、
特に手続きをしなくても、そのまま3年までスライドしての学習が可能になる制度です。
(テキストの印刷代は別途必要)
勉強を開始する時点では、ストレートで合格できるとは考えておらず、
複数年での受験を前提に考えていたため、
この制度を導入していることが、診断士ゼミナールを選ぶ決め手となりました。
先ほど書いたように、経営法務、経営情報システムから学習を開始していたのも、
科目合格制度を活用する前提に立って、2次試験に絡まない科目から片付けようと
していたからにほかなりません。
科目合格制度については、中小企業診断士協会が作成したこちらのpdfが詳しいです。
背水の陣を敷いたふりして、逃げ道は作っておいたってことやな


部長?なぜここに?
いや、現実的なラインも見ながら動いていたって言ってくださいよ…
まとめ
私のこの時期の混乱っぷりを、少しはご笑覧いただけたのではないでしょうか。
こんな状態からでも、8月には戦える状態まで持っていけるんです。
(一次に注力しすぎてしまい、必要以上の点数を取ったはいいものの、
二次試験でまた大いに苦しむことになるのですが、それはまた別の機会に)
この記事が、中小記診断士の試験勉強を始めたばかりで不安に駆られている方や、
モチベーションが上がりきらない人に、何かをお届けできていれば幸いです。
明日は、いつも心の余裕を忘れない、まっちの登場です。お楽しみに!





