【今から間に合う事例Ⅳ】NPV3分以上クッキング!
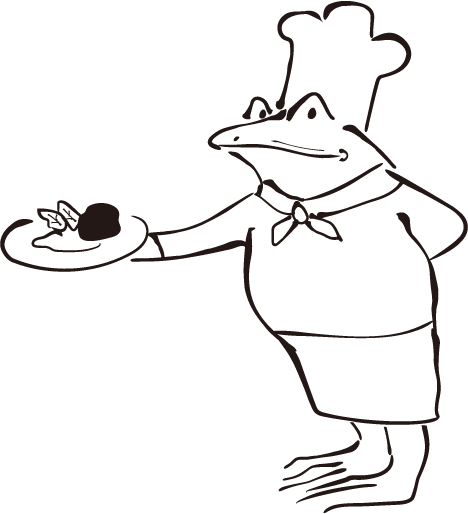
ブログをご覧の皆様、こんにちは。
「配られたカードで勝負するっきゃないのさ」ストレート合格ナビゲーターのちーたーです。
さて皆さん、勉強は捗っておりますでしょうか?
1年前の私のように、事例Ⅰ~Ⅲの過去問を解いて「なんだこりゃ!〇ソゲーじゃねぇか!」とさじを投げたりしていないでしょうか?
事例Ⅰ~Ⅲの中で「この事例はいけるかも?!」と思えるものがあればいいのですが、私みたいな事例Ⅰ~Ⅲのどれもできない人は、果たしてどうすればいいのでしょうか?
答えは単純。事例Ⅳをバッキバキに鍛え上げることです。
勿論、事例Ⅰ~Ⅲで開眼?とやらが訪れて点数が上がる可能性もあるので、事例Ⅰ~Ⅲを諦めちゃいけないわけですが、開眼?とやらが訪れず、私のように無明の闇の中で受験することになる可能性も十分あります。その時、事例Ⅳを鍛え上げていると、強い武器になります。
そして、事例Ⅳを強い武器にするには、避けては通れない論点があります。
そう、NPVです。
事例Ⅰ~Ⅲができる方であれば「NPVは難しいから、計算過程とか当てやすいところだけ当てて点数稼げばいい」という戦略は成り立ちます。
しかし、事例Ⅰ~Ⅲのどれも得意でない方は、その戦略では少々厳しいでしょう。
事例Ⅰ~Ⅲでなんとかしがみついて、50点台前半から後半を死守しつつ、事例Ⅳで合格ラインに達するためには、最低でも70点は欲しいところです。
そして、事例Ⅳで7割以上取ろうと思えば、NPVを避けては通れないのです!
よって、今回のテーマは「NPV3分以上クッキング!」とさせて頂きます。
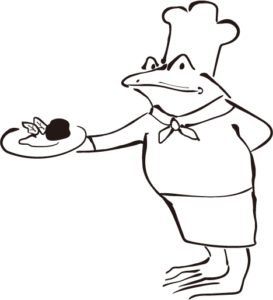
(~♪ 例の音楽。皆さん、それぞれ頭の中で鳴らして下さい。)
はい、それではNPV調理法の手順をお伝え致します。
29年の過去問の第3問を確認しながら読んで頂くとより一層効果的です。
① 税率、単位、四捨五入などの前提条件の確認。
② 設備ごとの取得価額、簿価、耐用年数、残存価額、償却方法の確認。
この時、毎年の減価償却費は計算しちゃって下さい。大体、定額法ですので。
29年だと次のような感じです。
旧設備 取? 簿50 残耐5 定額 残0 減10
新設備 取200 耐5 定額 残0 減40
旧設備は取得価額と耐用年数が不明ですが、簿価と残存耐用年数がわかれば問題なしです。
③ 各案ごとの収益、費用、設備の処分費用の確認
④ 横線を引き、フォーマットを作成。
フォーマット作成のために使う材料としては、初期投資、収益、費用、減価償却費、設備の処分費用、残存価額(売却であれば売却収入)、売却であれば売却損、というところです。これらの情報を設問文から抜き出してまとめればいいのです。
私の場合、A案とB案があれば、それぞれの投資案ごとにフォーマットを書きます。
それぞれの案の差額を記入してフォーマットを1つで済ませ、最初から節税効果も加味して計算してしまうたーるみたいなタイプもいますが、私はあんまり省略せずに地道に書く方です。
出来上がったフォーマットがこちらです。

縦列の項目の順番は特に決めていないのですが、気になるものはさっさと書いてしまうのがこだわりと言えばこだわりと言えるかもしれません。
新設備の投資額を書いたら、すぐ下にその新設備の減価償却費を書いてしまうこと。
除却損や処分費もさっさと書いてしまいます。
わかりにくいのは、投資する場合の方の、×1末の税金の額でしょうか。
120×30%=36じゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、×1初のところに旧設備の処分費用10がありますね。
この処分費用の税金への影響を考慮しないといけません。
従って、(120-10)×30%=33なんです。
キャッシュアウトのタイミングとしては×1初なので、処分費用を×1末に持ってきたりしてはいけませんよ。あくまでも、税金への影響が×1末というだけなのです。
ここでちょっとブレイク。
新設備に投資する場合の、旧設備の処分費用の税金への影響がいつ生じるか、問題文中から探してみてください。
おわかりいただけただろうか・・・?
そう、問題文中には書いてありません。
「旧機械設備の除却損の税金への影響は第 X1 年度末に生じる」とは書いてありますし、
「耐用年数経過後(5年後)の設備処分支出は(中略)この支出および税金への影響は第 X5 年度末に生じる」とも書いてあります。
しかし、新設備に投資する場合の、旧設備の処分費用の税金への影響がいつ生じるかは書いてありません。
ここは少し、判断を要する部分だったかもしれませんね。
まぁ、税金への影響だとか、節税効果だとかは、期末に生じると思っておけば間違いないと思います。
ここから下の手順は、厳密には「フォーマットを書く」という行為に包含されていますが、それだと少しわかりにくいと思うので、明確化の意味で記載します。
⑤ 税引前利益を計算
⑥ 税引前利益までの項目の抜け漏れがないか再度確認
⑦ 税金を計算し、税引後利益を算出
⑧ 非資金支出項目(減価償却費、除却損)を足し戻す
⑨ それぞれの年のCFに現価係数を乗じて合計し、正味現在価値を算出
ハイ!出来上がりです!
勝負の分かれ目は、税引後利益を計算するところまでだと思います。
税引前利益で安心してはいけない、というところが29年の教訓かと。
ただ、税金は期末!と知っておけばいいだけなので、難しく考える必要はないと思います。
NPVは基本的にルーティーンです。難しいことは何もないのです。
NPVが難なくできるレベルに達すれば、他の計算問題も簡単に思えてきます。
そうなれば、70点は堅いです。事例Ⅳで70点以上取れるようになれば、合格にグッと近づきます。
私のような、事例Ⅰ~Ⅲがク〇ゲーにしか思えない同志の方々!
某バスケ漫画風に言うと、
「こんなク〇ゲーに阻まれてどーする。事例Ⅳこそ凡人の生きる道なんだよ!!」
是非、NPVを自分のものにして下さいね!
さて次回は、まったりゆっくり独学派★多年度生合格ナビゲーターのかずさ の登場です。
前回のかずさのブログ、良かったですね(私に熱血疑惑がかけられていた事以外は)。
事例Ⅳの重要性がデータで裏付けされていて、納得感のある内容だったと思います。
これは次回も期待できますね! お楽しみに!





