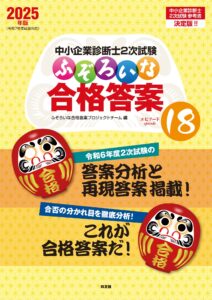ふぞろいな1次試験勉強方法!おかなつ編 ~1週間で1科目Inputを叶えるパワー系勉強法~
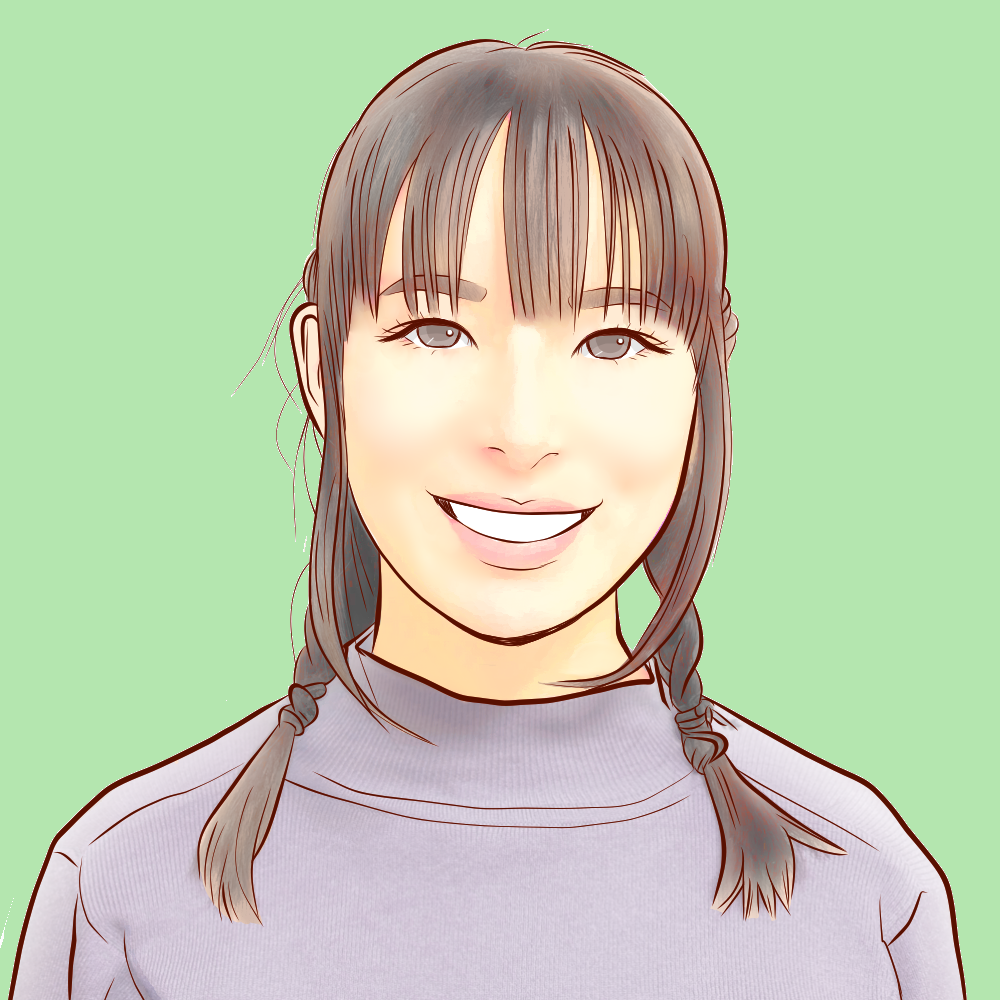
自己紹介ぶりの方はお久しぶりでございます!
初見の方ははじめまして!事務局と事例Ⅳの分析を担当していた“おかなつ”です。
(自己紹介は宜しければこちらから。)
私が試験を決意したのは令和3年の4月初旬でした。
試験当日まであと4か月…と時間がなかったので、いかに早く、されど深くInputとOutputを終えられるか、追及した結果がこれから書く“パワー系”の勉強法でございます。
ふぞ17の他のメンバーには個性強めの勉強法と評されてしまいましたが、やる気と体力と少しの才能(?)があれば、実践できるはず!かも…
今からでもきっと間に合う! 五感を研ぎ澄ましてご賞味あれ!
目次
1次試験結果
【経済学・経済政策】70点台(R3)/100点
【財務・会計】80点台(R3)/100点
【企業経営理論】60点台(R3)/100点
【運営管理】60点台(R3)/100点
【経営法務】80点(R4)/100点
【経営情報システム】80点(R4)/100点
【中小企業経営・政策】80点(R4)/100点
※経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理はR4科目免除。R3の点数は断捨離しちゃって不明です。ごめんなさい。なお、R4の受験科目は揃いも揃って80点ピッタリでした~
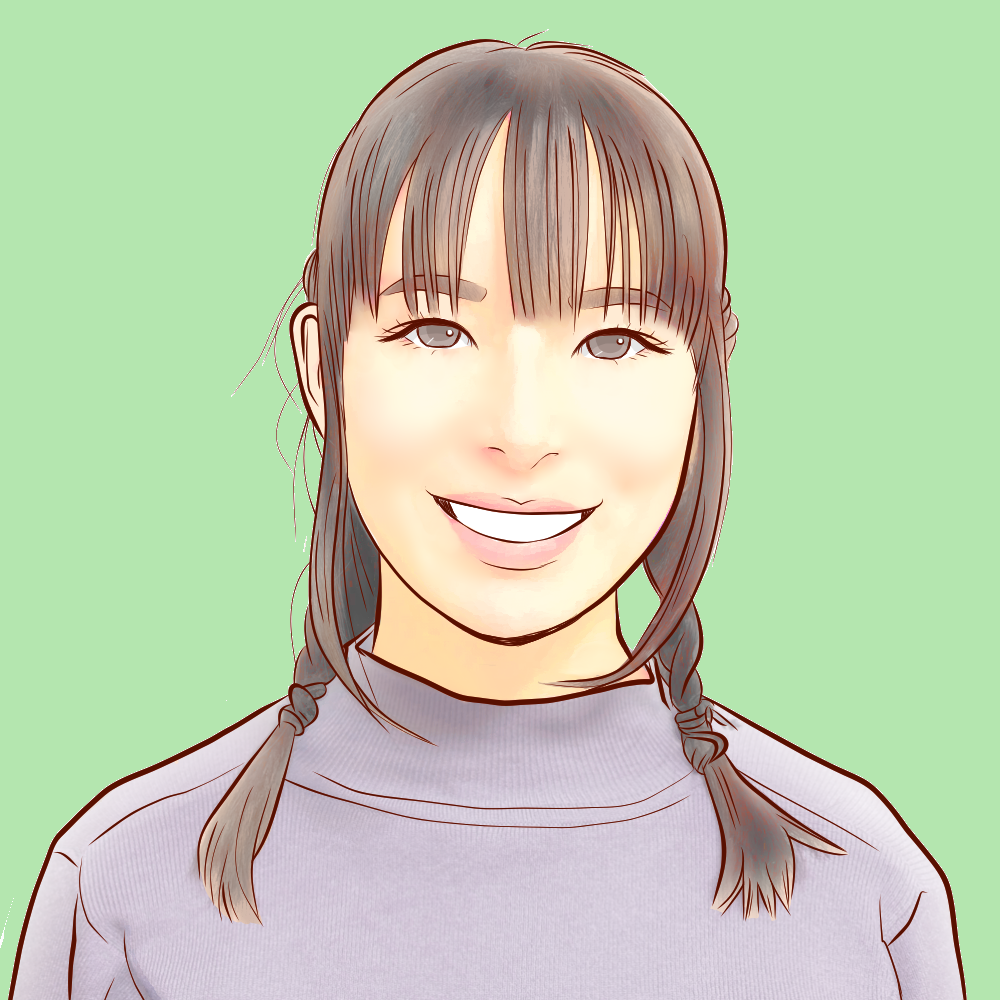
令和3年度の1次試験は、オブラートに包んで言うと体調不良でした…。1日目終えたからといって、はっちゃけるのはNGです(当たり前)
私自身の背景情報
自分の勉強への向き合い方や勉強スタイルが独特な部分が若干あるかも、という気がしたので、ご興味ある方がいらっしゃるかはさておき、少しだけ書かせてください。
■ 勉強に対する思い
昔から好きです。趣味です。
新しいことInputするの楽しい!
それが別の知識と繋がるともっと嬉しい!
もはや勉強するためにずっと学生でいたい!
■ 勉強スタイル
・目で覚える
・手で理解する
・耳で記憶を掘り起こす
→上記を同時並行&高速で回転させる。
思い返すと小学生の頃からあまり変わっていない気がします。
主に暗記系のテストは昔から得意なので、そのまま成長してしまったのかもしれません。
結果的に社会人でとても苦労しています(慟哭)
使用教材
先にまとめておきます。
この後の各章は教材ごとになっていますので、ご興味ある部分を読んでいただいても構いません。
①通信:診断士ゼミナール
②書籍:野網美帆子「一発合格まとめシート(前編・後編)」
③YouTubeチャンネル:「ダンシ君のサブノート」
④その他:過去問
なお、試験範囲のアップデートがあるため、R4は一発合格まとめシートの後編のみ、最新版を購入し直しました。
今年も試験範囲(正確には試験内容の表記)が変わっているようですね(リンク)。
過年度生で昨年の参考書を使っている方は要チェックです!
【教材① 通信講座】診断士ゼミナールの活用法
〇選んだ理由
冒頭に記載した通り、私が試験を決意したのが令和3年の4月初旬でした。
試験当日まで約3か月と時間がなかったため、素早く体系的に学べる通信講座の利用を決めました。
3年間の無料延長制度と、合格お祝い金制度があったことも、個人的には保険になり魅力的でした。
〇勉強法
とにかく早く一通り勉強を終わらせて、過去問演習に入りたかったので、朝5時に起きて24時間営業のファストフード店に行き、3時間勉強してから家に帰って在宅ワークする…という日々を続けていました。
診断士ゼミナールの動画はダウンロードしてアプリ再生が可能だったため、10倍速まで可能なアプリを活用し、デフォルトは3倍速で視聴していました(企業経営理論や財務会計、情報システムなど、取得資格や本業のお陰で基礎知識があるものは4倍速)。
結果、1科目1週間ずつで叩き込みました。
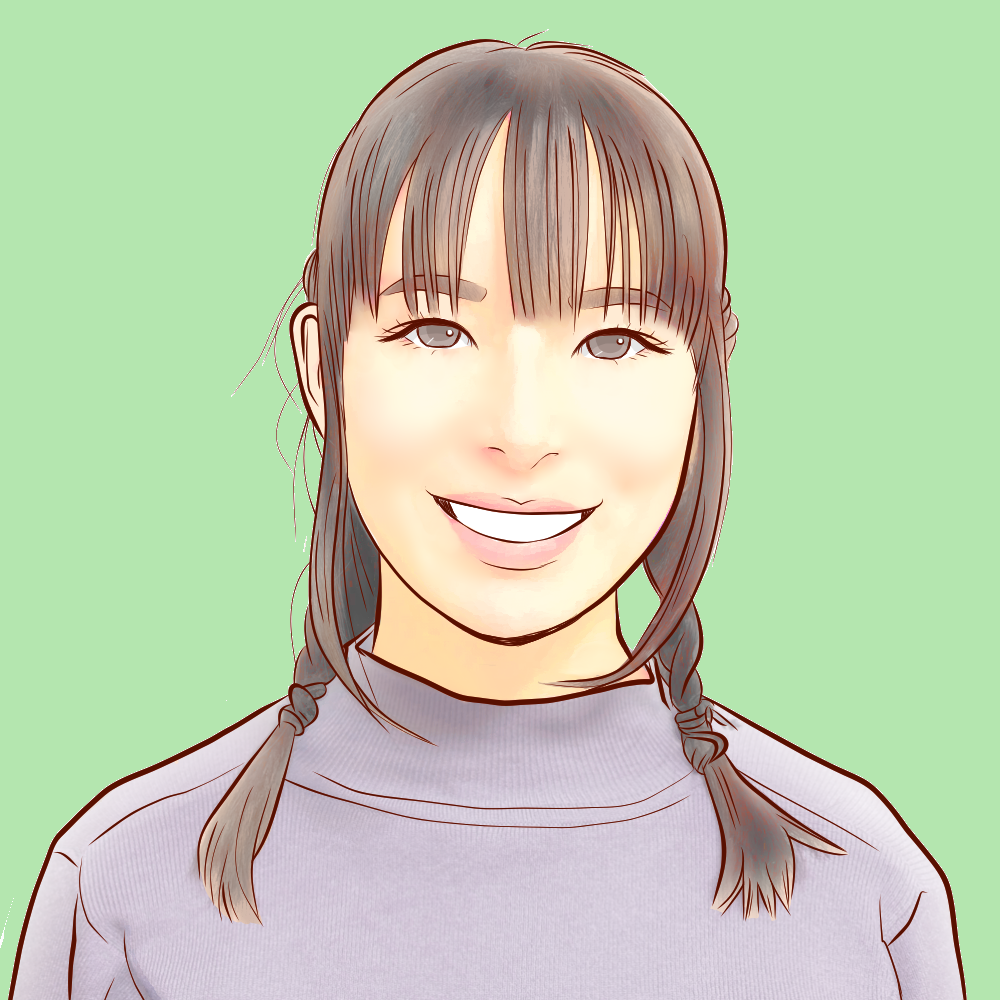
3倍・4倍速にすると異様な集中力を発揮できます。脳トレになったかも?
【教材② 書籍】「一発合格まとめシート」の活用法
〇選んだ理由
ビジュアルで1枚ずつにまとまっている、ということが何よりも魅力的でした。
私自身は比較的ビジュアルでものを覚える(過大評価して言うならば映像記憶する)ことが得意だったので、この参考書と出会ったときは「野網さんの後に生まれてよかった!」とまで思いました。
〇勉強法
とにかく「見る」時間を増やすことを重視し、1枚紙のデータをA5サイズに印刷し、あらゆるところで眺めていました。また、知識の定着度を上げる・上がったことを確認する工夫をしていました。
知識量0% :印刷した紙をそのまま見る
知識量1~70% :「イルカの暗記シート」というアプリを使い、デフォルトの赤文字から、その周りの黒字のところまで自分で緑ペンを引いて、隠す量を増やす
知識量71%~ : 1枚紙を思い出しながらA4の白紙にすべて書き出し、知識が定着しているか確認(ちなみに絵心皆無のため、文字と図形のみ)。
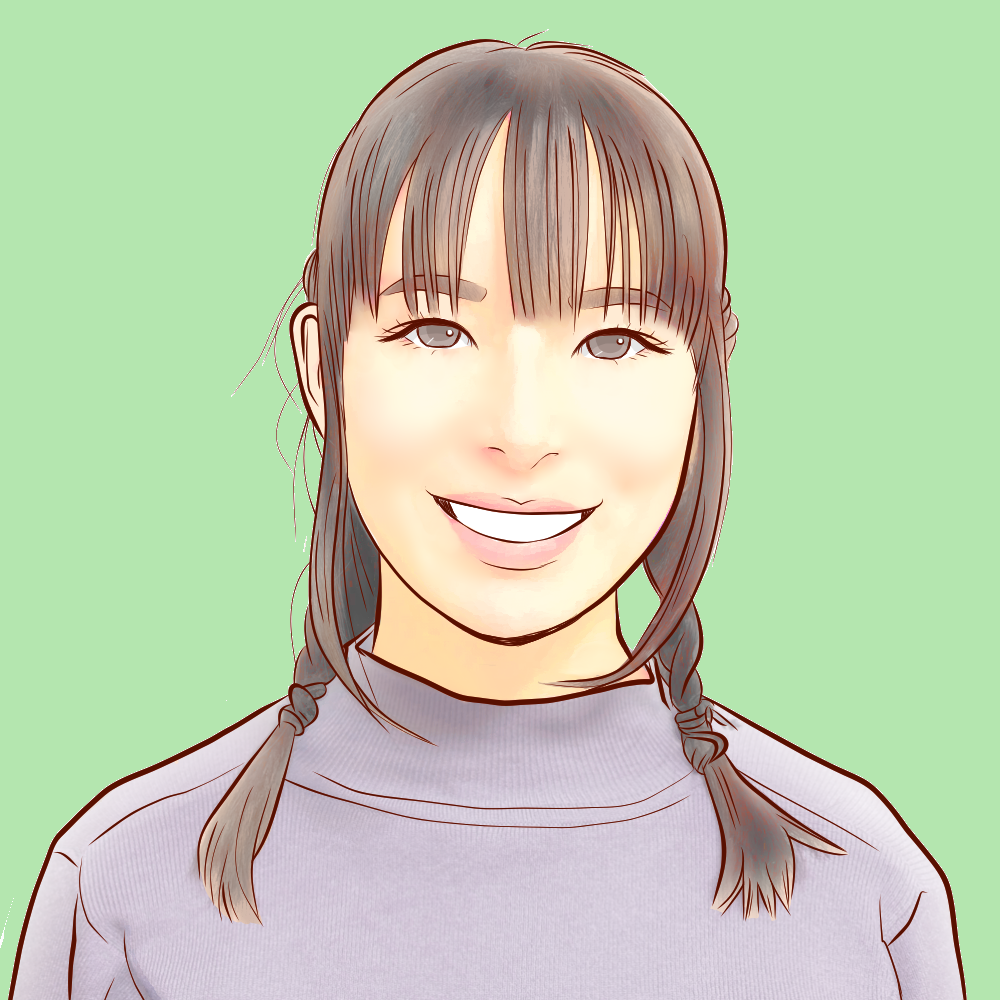
ラミネートの機材を買って印刷した紙をラミネートし、半身浴で眺めていたのは良い思い出です。半身浴をしていたのは後にも先にもあの時だけ。
【教材③ YouTube】「ダンシくんのサブノート」の活用法
〇選んだ理由
映像記憶が得意と言いつつ、やっぱり寝る前は電気を消したいし、満員電車は酔ってしまうから目を瞑りたい。
そんな願望をかなえてくれた、耳から一問一答の王道コンテンツでした。
〇勉強法
診断士ゼミナールの動画を見ているとき以外は、とにかく聞きまくる!を徹底していました。スピードはYouTubeの限界速度の2倍で聞いていました。
また、これが効果はあったかさておきですが、「まとめシート」を見ている時間は耳が空いていて勿体ない(?)という思考で、目は「まとめシート」、耳は「ダンシ君」という力業的なことをやっている時期もありました。
(一応、演習中に「これはダンシ君でこれを聞いていた時に見たまとめシートのここだ!」という記憶呼び起こし機能は果たしてくれました)
【教材④ その他】過去問の活用法
〇選んだ理由
経験上、一般的な資格試験は基本的に過去問演習が合格への最短だと考えています。過去問原理主義者なので、過去問を使わないという選択肢はありませんでした。ですよね?
〇勉強法
診断士ゼミナールで一通りInputした後に取り組み始めました。
解いた年数:
◆ 経済学、財務会計、企業経営理論、運営管理:10年分
◆ 経営法務、情報システム:5年分
◆ 中小企業政策:1年分
周回方法:
✓ 1周目:とりあえず解く。時間かけない。絶対に間違えない自信があるところと、解けない可能性が高い問題の振り分けが主目的。得点率3割でも全然OK。間違えた問題はまとめシートを使って復習。1日に3~4科目くらい。
✓ 2周目:5割とれたらラッキーというテンションで解く。今回は、選択肢のどこがどう間違えているか、まで指摘できるか、知識の定着度合いを確認することが主目的。
間違えた問題はまとめシートで復習し、該当テーマのまとめシートの部分を完コピ。
1日に2~3科目くらい
✓ 3週目~:6割以上を安定的にとれるまで解いてミスを復習しての繰り返し。1日に2~3科目くらい。
終わりに
結局のところ、勉強法は自分に合うものを見つけるまでが一番大変であり、あとはそれを実行するだけ(それはそれで大変?)だと思います。
私の勉強方法もOne of themですので、試行錯誤の一助になれば幸いです。
明日は、数奇な人生を送っているらしい“もろ”の登場です!
「2次試験は国語の試験だ」と力強く割り切っていた彼は、1次試験をどう捉えていたのか?乞うご期待!