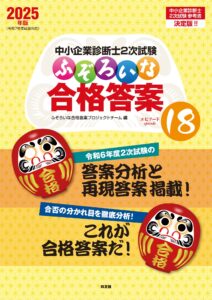テリー流「ファイナルペーパー(事例Ⅲ・事例Ⅳ)」の大公開!!
読者のみなさま、こんにちは。名古屋から情報発信!頑張るあなたと伴走します!ストレート合格ナビゲーターのテリーです。
2次試験まで、残り1ヶ月となりました。まだまだ時間が欲しいと思っている方、早く試験を受けたいという方、モチベーションがなかなか上がらない方、現在の状況はそれぞれかと思いますが、まだ1ヶ月あります。試験当日を迎えたときに、これだけ頑張ったんだから大丈夫と言えるまで、最後まで駆け抜けましょう。
さて、本日は、前回の続きで、ファイナルペーパーについてご紹介させていただきます。事例Ⅲと事例Ⅳの特徴から見ていきます。それでは早速いきましょう~。
目次
■各事例の特徴(事例Ⅲ)
事例Ⅲは、生産現場のイメージが湧かず、なかなか得点を安定することができず、どちらかと言えば苦手意識がありました。問題のパターンを意識してから、少しずつ安定するようになりましたので、設問の全体像を捉えるといいかもしれません。では、実際の中身をご覧ください。
★第1問目はC社の強み(まれに弱みも)が関係し、第2・3問目は現場のオペレーションの改善が問われ、最終問題は第1問目で解答したC社の強み、機会、経営課題を捉えて、新たな戦略を打ち出すのが、オーソドックスな展開。最終問題では、C社の弱みや課題については、既に解決されている前提で考える(第2・3問目で解決済み)。なお、「経営資源に着目して」と問われることがあるが、その際、経営資源が不足しているのであれば(例えば:営業力不足)、補完することを忘れない。事例Ⅰと同様、レイヤーで考えると分かりやすい(全体戦略なのか、現場のオペレーションなのか)。
★現場のオペレーション改善は様々あるが、「生産管理」・「生産計画」に関するものが多く問われ、問題点・課題と対応策を解答する(字数が多い設問もあり、因果関係をはっきりさせる必要がある)。
★生産計画とは、「いつ、いくつ」作るのか計画、これがないと安定した品質(Q)、コスト(C)、納期(D)を守れないので必要。
★QCDの観点では、短期的にはC・Dの改善、長期的にはQの改善を意識する。※もともとQはある企業が前提?!
★事例Ⅲは、現場のイメージが湧きにくいため、一次知識の土俵に持っていくことが特に重要。使える知識をストックしていく。※3S、5S、ECRSの原則、SLPによりレイアウト改善、生産形態、ABC分析など
★課題・問題・原因・改善策が問われた場合、図式化すると分かりやすい。問題点は、何と何が生じているかで考える(2つあることを意識)。原因も2つあることを意識すべし。①何かの量的な変化により、問題点の量が増加するパターン、②これまでも問題は発生していたが、何もしておらず、原因を追究したら判明した(過去問では、カット野菜事例の特性要因図)の2パターンがある。どのパターンなのか意識してみると、改善の方向性がみえる場合がある。※図式化する際の注意点・・・図式化すると何を書けばいいか明確になるものの、時間をかけすぎないよう時間配分には気を付けよう。
★事例Ⅲでは、当たり前のことが出来ていない事例企業を改善提案する。明らかにおかしい問題点は、それを裏返しすることが改善になる。
例:作業が担当者によってバラバラ → 標準化 → マニュアル作成・共有 → OJT教育
工具が散らばっている → 5S
段取り替えが多い → 外段取り化・シングル段取り化
営業の打ち合わせが非効率 → 一元管理(DB化)→ 共有化 → IT活用
★問題だと認識できるものの、その改善には原因特定が必要。
例:生産性が低下している → 何らかの理由で、設備の稼働率が低下
作業員の残業が発生している → 顧客からの納期短縮要望がつよい
品質が低下(あまりない) → 品質チェック方法がおかしい
作業待ちがおおい → 生産設備の稼働順番がおかしい
過剰な在庫を抱えている → 発注方法が適当(発注量が定まっていない、適正在庫を設定)
★図が与件文に記載されるケースがあるが(初見でも焦らず)、設問要求に関係あるか確認。
以上が、事例Ⅲの内容になります。令和元年度の本試験では、直接「問題点」「課題」「改善点」といった問われ方はされず、「生産面での効果とリスク」「在り方」「生産管理上どのような検討が必要か」といった形で出題されましたが、設問全体の構成はこれまでの過去問とあまり変わらなかった印象です。今年はどのような問われ方がされるか分かりませんが、問題の構造や一次知識に着目して、乗り切っていきましょう。
■各事例の特徴(事例Ⅳ)
事例Ⅳについては、特徴の把握というよりも、いかにミスを防ぐかという観点で、まとめていました。自分がよくミスするポイントをまずは書いて、意識していましたので、みなさまもよくミスするようなところは書き出して、その対策を実践できるよう、具体的な内容を書くといいかもしれません。では、事例Ⅳの特徴をご覧ください。
★事例のよく間違えるポイント(対策指針)
★キャッシュフローを求める際、(1-税率)ではなく、税率をそのまま掛けてしまう。
⇒対策(行動指針):必ず公式を書いて、間違えがないように計算する。
★問題文の解答に関係する重大な記載を見落とす
⇒対策(行動指針):あれっと思ったところは、マーカーで引き、間違えがないかチェックする。例:小数点の処理
★取り替え投資計算において、増減を意識することなく、そのまま計算してしまう。
⇒対策(行動指針):求められてる計算プロセスを確認し、何が問われているか確認をした上で処理する。
★設問2がある際に、設問1を間違うと設問2も五月雨式に間違えてしまう。
⇒対策(行動指針):まずは設問間のつながりがあるか確認し、設問1を特に重点的に考え、処理手順を何度も確認する。
★余白に書いた数字を取り間違えて、違う数値を計算プロセスに入れてしまうため、答えがあわない。
⇒計算プロセスを余白に書いて、数字の取り間違えが発生していないか何度も確認する(余白には綺麗に書こう)。
★経営分析(収益性・効率性・安全性の3つの視点で疑え)
テクニック①・・・同業他社比較の収益性比較では、同業他社/D社を実施し、その値と比較した時に変な値が出た時は要注意。これは、あくまでも困った時の奥の手。
テクニック②・・・与件文や財務諸表により、どうしても判別がつかない場合、収益性は売上高総利益率、安全性は自己資本比率、効率性は有形固定資産回転率を書くことを決めておく。
★経営分析記述対応(記載する際の型を決めておく)
①有形固定資産回転率 「設備が稼働しておらず」or「過剰な投資で」それに見合った売上があげられておらず、効率性が悪化。
②負債比率 〇〇への投資を借入したため、負債比率が悪化し、安全性が低い。
自己資本比率 増資により払込資本が増加し(内部留保が手厚く)、安全性が高い。
③売上高経常利益率 借入金の増加により、支払利息が増加し、収益性が悪化。
売上高営業利益率 販管費の増加により、営業利益が減少し、収益性が悪化。
★CVP分析
損益分岐点売上高 S(売上)-α(変動費率)S-FC(固定費)=0
※FCをもとにした連立方程式で計算する問題あり、感度分析は何が変化するか丁寧に確認。
★NPV
☆取り替え投資の場合の注意事項
既存の設備をそのまま使用した場合(a)と新規設備に取り替えした場合(b)の差額(増分)キャッシュフローに着目
処理①減価償却費の差分をチェック (b)-(a)・・・(c)
処理②新設備に取り替えた際の効率額 (CIF-COF)=(d)
処理③増分キャッシュフローの計算 (d-c)×(1-税率)+減価償却費
処理④既存設備の売却額に着目(おそらく問題文に記載があり)
処理⑤既存設備の●年後(新設備の対応年数終了:通常5年のケースが多い)の売却収入を計算。
処理⑥各期の算出されたキャッシュフローの現在価値に割り戻して計算。
処理⑦処理⑥で求めた数値から(初期の投資額―既存設備の売却収入)を差し引く。
★キャッシュフロー計算書の覚え方
営業CF:ヒキニゲ ヒキアテ ギャクソウ ウンテン(ケイカン・その他) リソク ハイトウ ホウジンゼイ
投資CF:ユウコ(有形固定資産の購入・売却)が ユウカ(投資有価証券の購入・売却)に カシツケタ
財務CF:タカリ(短期借入金) チカリ(長期借入金) シャ(社債)カブ(株式)ハイ(配当金支払)
☆最終チェックする方法 ①現金預金の前期・当期の差が、営業CF+投資CF+財務CFになる。検算可。
以上が、事例Ⅳになります。事例Ⅳはとにかく慣れることに尽きると思います。確か、10月に入ってから私はTACの「事例Ⅳ特訓(動画)」を受講し、最後的な仕上げをしていました。直前期に新しいことをやってもいいのかと迷いましたが、やらずに後悔するのも嫌でしたので、とにかくやれることはやろうと思い受講しました。皆さまも、最後までやるべきカリキュラムを今一度見直してはいかがでしょうか。
■各事例の知識
各事例の知識は、これまで学習してきたテキストをコピーしたものをそのまま使用していましたので、すべてを紹介することはできませんが、知識といっても一次知識で学習した内容を箇条書きにしていました。箇条書きしたものを頭に思い浮かべ、すぐに解答が出てくるように訓練していました。今回は事例Ⅰだけご紹介させていただきます。基本どれもオーソドックスなものかと思います。
★競争戦略(ポーターの戦略論 ※コストリーダーシップは中小企業ではほぼありえない)
★VRIO分析(経路依存性⇒長年培ってきた強みがある)
★経営環境
SWOT分析(強み・成長要因・競争優位性など問われ方は多数)
PEST分析(政治的、経済的、社会的、技術的)
3C分析(顧客・競合・自社)
5フォース分析(買い手・売り手・新規参入者・代替品・業界内競争)
★経営管理(PDS管理・PDCA管理)
★組織の成立要件(共通目的・貢献意欲・コミュニケーション)
★組織の5原則(専門化の原則・責任権限一致の原則・統制範囲の原則・命令統一性の原則・例外の原則)
★組織構造(機能部別組織・事業部制組織・マトリックス組織・プロジェクトチーム・タスクフォース・M&A)
★組織行動(組織風土・組織文化・組織学習)
★モチベーション(動機付け)・モラール(士気)向上
★組織文化・風土
★権限委譲・職務拡大・職務充実・集団の凝集性・集団浅慮
★人事施策(茶化)
①採用(新卒・中途採用・再雇用・女性活用・非正規雇用者・海外人材)
②配置(ジョブローテーション、社内公募制度、キャリア開発制度、複線型人事制度)
③報酬(年功序列型・成果主義型)
④育成(OJT・OffJT・自己啓発・社内ベンチャー・社外セミナー・Eラーニング)
⑤評価(透明性・公平性・納得性)・MBO・社員表彰制度・コンピテンシー評価
事例Ⅰはざっとこんなところでしょうか。組織構造などは頻出論点ですので、それぞれのメリット・デメリットがすぐに思い浮かぶようにしていました。あれもこれもついつい頭に詰め込みたくなりますが、それよりも確実にアウトプットできる状態にまでなった知識を持っていくようにするといいかと思います。
■自分への励まし
ファイナルペーパーもあともう少しになります。最後のご紹介は、「自分への励まし」です。励ましと言っても、大袈裟なものでなく、一言ぐらいです。簡単に紹介しますと「自信を持とう」「最後の最後まで粘ろう」「終わった事例はとっとと忘れて、次の事例に集中しよう」「気分転換して糖分を取ろう」といったものです。
どうしても終わった事例に頭が引っ張られ、あれはよかったのかなとか、あれはミスったなとか、全然歯が立たなかったなとか、いろんなことを考えてしまいますが、一度解答用紙を提出してしまえば、あとは手の出しようがありません。振り返るのは、試験が終わってから、いくらでも振り返ることができますので、少なくとも事例の途中では、ネガティブなことはさておき、次の事例に集中することを心掛けるようにするといいかもしれません。是非、「自分への励まし」もファイナルペーパーに入れると、心を平穏に保って、事例に向き合えるように思いますので、取り入れてはいかがでしょうか。
■まとめ
それでは2回にわたってご紹介したファイナルペーパーのまとめをさせていただきます。
✔ 心の拠り所になれば、ファイナルペーパーには何を書いて自由。ただし、まとめることが目的にならないように注意しよう!!
✔ 詰め込み過ぎたくなる気持ちをおさえ、必要最低限にしよう!!
✔ 冷静に試験と向き合うために、「自分への励まし」を書いておこう!!
本日もお付き合いいただきありがとうございました。残された日々を噛みしめながら、やろうと思ったことを実現させ、試験当日を迎えるようにしましょう。試験までのラストスパートをともに頑張っていきましょう。明日は、知らないところで、果敢にチャレンジしていたYUMAの登場です。お楽しみに♪♪